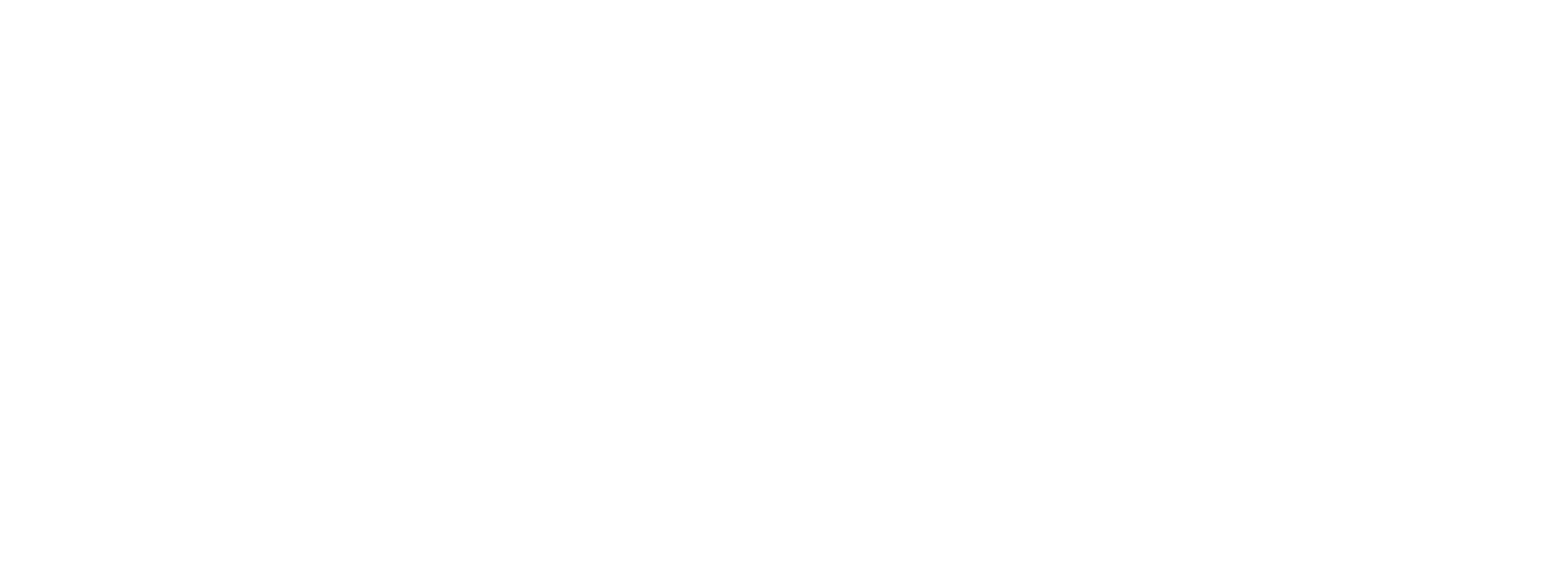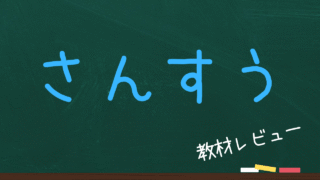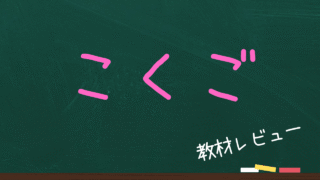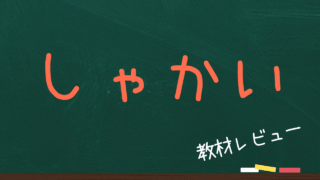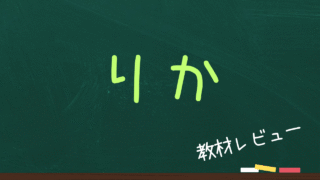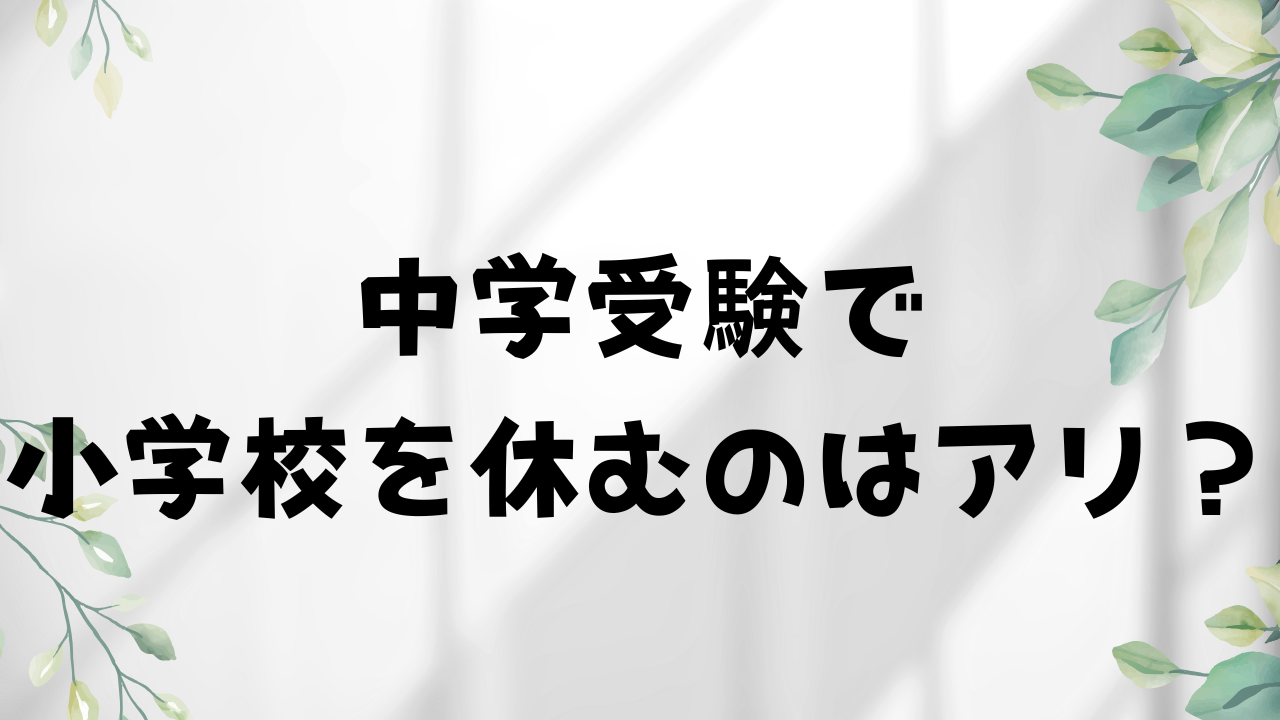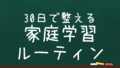中学受験で学校を休むのはアリ? わが家の実例と進め方

中学受験で学校を休んでもいいのかな?
そんな迷いのある方へ。
わが家は入試シーズン、小学校を休むという選択を取りました。
12月入試に向けて、思い切って11月は学校をお休みしました。
この記事は、わが家の実体験をもとに書いています。
(目的・期間・学校への伝え方)・休んだ間にやったこと
(勉強の進め方と1か月の組み立て)・子どもと自分のメンタルケア
ぽんままの、受験前のありのままの記録です。
ご家庭や学校のルールはそれぞれです。
校則や欠席の扱いは、事前に先生に確認してください。
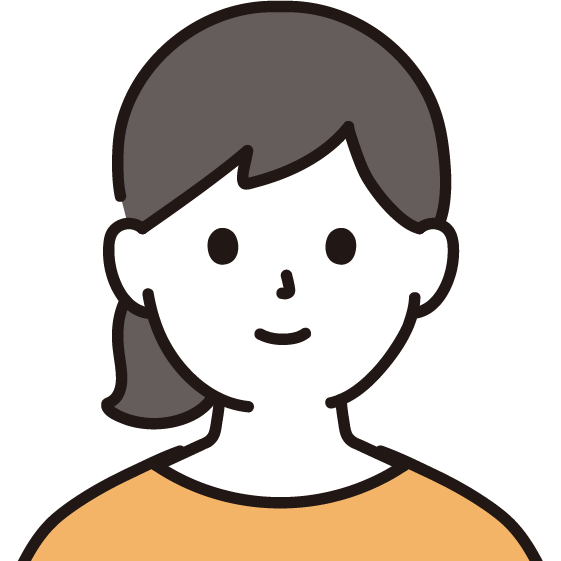
この記事が、みなさんの迷いを少しでも減らし、家族で納得して前に進むためのヒントになればうれしいです。
休む前に考えたこと
休む目的をはっきりさせる
「なぜ休むのか」を家で言葉にしました。
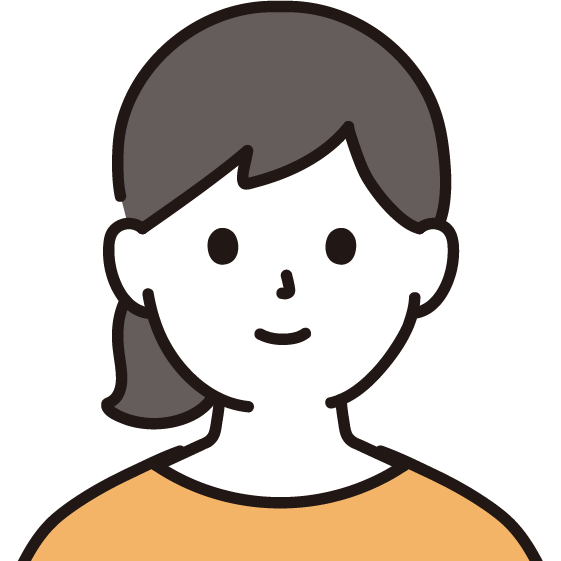
わが家の答えは「志望校の対策に集中するため」
ただの勉強時間の確保ではなく、合格につなげるため『勉強に時間を集める』、という約束を親子で交わしました。
目的がはっきりすると、迷いが減り、毎日の行動が決めやすくなります。
志望校対策に集中するためと決めた
志望校は1校のみ、面接なし。
だからこそ「その学校の出題に寄せる」ことに全振りしました。
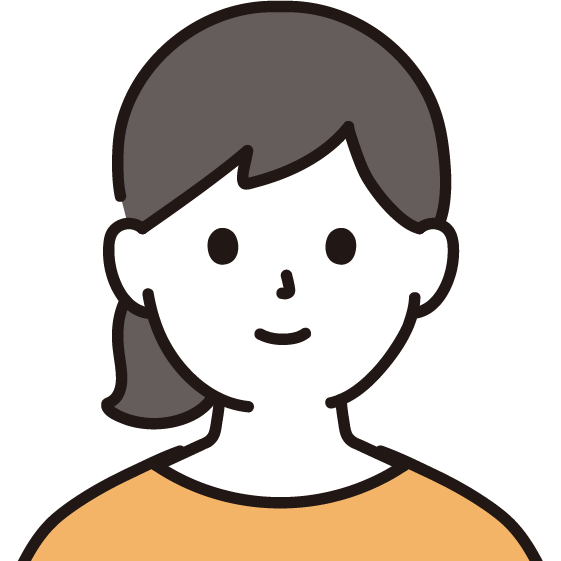
やらないことも決めて、気持ちと時間のムダを徹底的に減らしました。
どのくらい休むかを家で決める
休む期間は先に決めました。
ダラダラ伸びると学校にも家にも負担がかかります。
日付で区切ることで、計画が立てやすくなります。
12月受験だったので11月をまるっと休んだ
うちは12月受験だったので、前の月の11月を1か月まとめて休みました。
休む前に担任の先生へ相談し、宿題や連絡の受け取り方法も決めてから入りました。
学校への連絡と配慮
学校には早めに、シンプルに伝えました。
家庭の事情を長く説明しなくても大丈夫。
大切なのは、先生が困らない段取りを一緒に考えることでした。
担任への伝え方・宿題や連絡物の受け取り・友だちへのひとこと
「〇月はお休みします。宿題は家で進めます。連絡物は保護者が受け取りに行きます」と短く。
友だちには「今月は受験でお休み。終わったら遊ぼうね」と一言だけ。
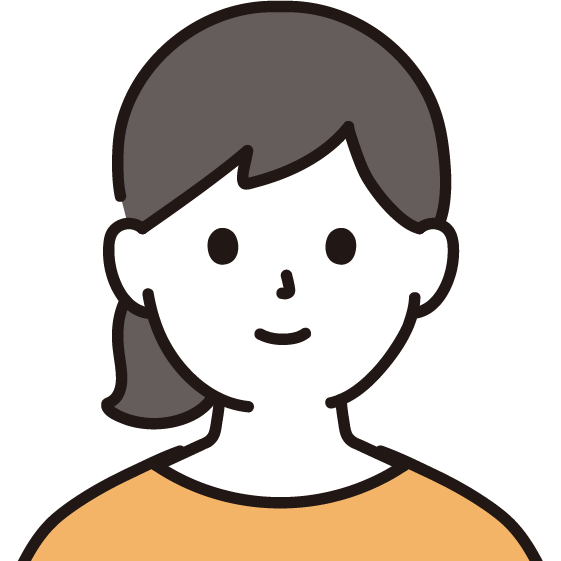
息子の担任の先生は”前向きに理解”をしてくれて、校長先生も『がんばれ受験生!』と大きな声で応援してくれました。
この経験も、息子にとっては「みんな、応援してくれている」と実感できる大切な経験でした。
休む間の学びの方針(うちは1校受験・面接なし)
やることをしぼる
広く浅くの勉強は、9月くらいにやめました。
志望校の科目と出題のクセに合わせて、やる・やらないを分けます。
全部やろうとすると、どれも中途半端になります。
出題の傾向をつかみ、やらないことも決める
たとえば「長い記述がほぼ出ない」「計算の比重が高い」など。
傾向に合わない問題集は、この期間は思い切って外しました。
過去問10年分を軸にする
学校を休んでいる期間、学びの中心は過去問。
10年分を用意し、年度や大問で切って計画に落としました。
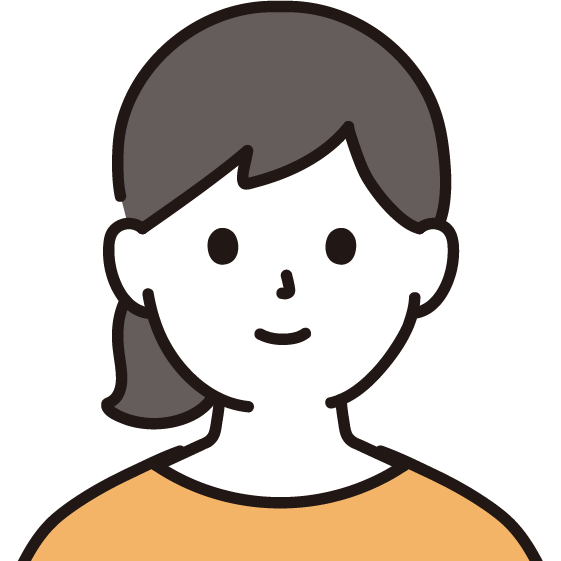
過去問は「現在地」と「合格ライン」をつなぐ地図のようなものです。ただし、過去問を解けるようにすることがゴールではないことを、しっかり理解して取り組みましょう。
時間を計って解く/採点→ふり返り→やり直し
本番と同じ時間で解き、すぐ採点。
間違いは「原因」を一言で書き出します。
思い込み、読み落とし、計算ミス…原因ごとに対策を決め、同じミスを繰り返さない仕組みにしました。
過去問→まちがえた単元の演習をくり返す
やり直しは「過去問に戻る前に、単元へ戻る」流れにしました。
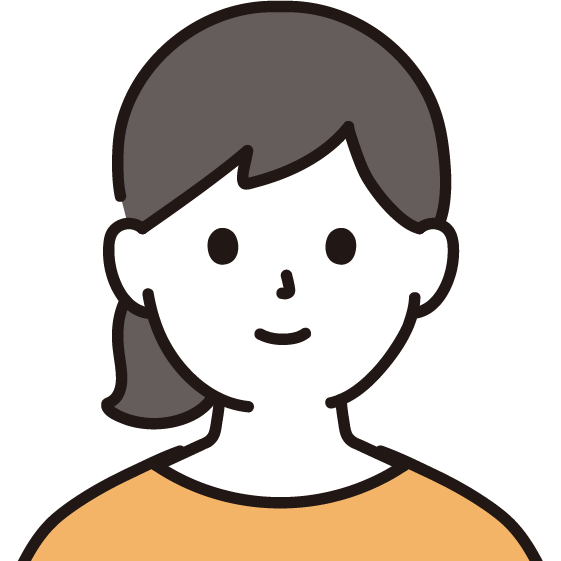
点が線になり、線が面になる感じです。この時期は、単元の理解を深めることがとても重要です。
「自由自在」で要点確認/「でる順過去問」で反復
要点の確認は『自由自在』、手を動かす反復は『でる順過去問』。
この二つで、弱点の穴を素早くふさぎました。
暗記系(社会・理科・漢字)は回転数重視で、毎日テスト感覚で回しました。
参考書と問題集のセット使いをおすすめします。それぞれ章立てが対応しているので、『調べる→演習』の流れがスムーズです。
偏差値65なら『自由自在』中心でOK?参考書の実力を口コミと特徴で確かめる!
中学入試 自由自在 問題集の評判は?4科×3ステップの特徴と使い方【別冊解答が充実】
≪暗記系≫
社会、理科は赤シートでスピード&回転数重視。漢字はシンプルな問題集をとにかく回転させることに集中しました。
社会・・・サピックスメソッド「社会コアプラス」口コミ・評判と効果的な使い方
理科・・・サピックスメソッド「理科コアプラス」口コミ・評判と効果的な使い方
漢字・・・中学入試 でる順過去問 漢字 合格への2610問(工事中)
1か月の回し方(直前期モデル)
週ごとの計画
1週目は全体チェック、2〜3週目は弱点つぶし、4週目は仕上げ。
本番に近づくほど新しいことは減らし、ミスの芽だけをつぶしました。
1週目:全体を見る/2〜3週目:弱点つぶし/4週目:仕上げ
1週目で「どこを落としやすいか」を洗い出し、2〜3週目で同じ型の演習を重ねました。
4週目は本番の時刻に合わせて演習し、体内時計も整えました。
1日の流れ
午前に重い科目、午後は演習、夜は暗記。
決めておくと迷いません。
体力の波も読みながら、無理をしないことを優先しました。
午前:過去問/午後:演習/夜:暗記(社会・理科・漢字)
夜は長くやらず、回転重視。眠い頭で新しいことは入れません。
覚えるものは朝とすき間時間に回しました。
休息日の入れ方
この時期は子どもと自分のメンタルケアもとても大切。
休む計画も予定表に先に書きました。
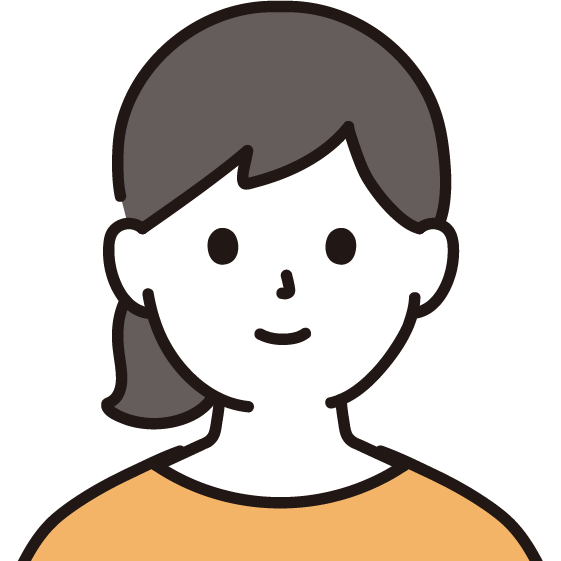
やる気が落ちた時に休むのではなく、「休む計画」を守るほうが回復が早かったです。
体と心を休める小休止を入れる
(少し買い物に付き合ってもらう)
・ストレッチ
(ちょっとふざけながら、笑顔で)
・甘いもの少し
(ラムネやグミがおすすめ。集中力UP)
10〜20分の小休止で、集中が戻りました。
心のケアとつながりの保ち方
いちばんつらかったこと
息子がいちばんつらかったのは「友だちと遊べないこと」でした。
みんなで映画に行った話を聞いて、涙をこらえた日もありました。
その気持ちは大事に受け止めました。
友だちと遊べないのがつらい(映画に行けなかった話)
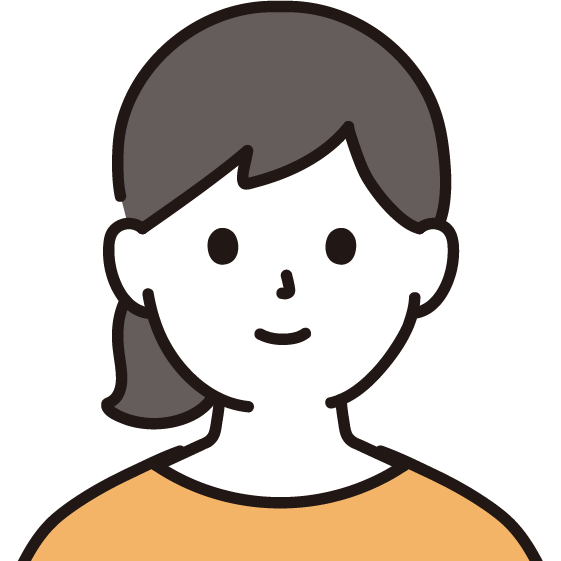
「終わったら、いちばんに映画に行こう」と伝えました。
すると、『ディズニーとユニバがいい~』と息子・・。
首都圏在住のぽんまま家。
ユニバは諦めてもらって、映画とディズニーで決着しました。笑”
先の楽しみがあるだけで、ふんばれることがあります。
気持ちの整え方
気持ちが落ちた日は、無理に詰めませんでした。
短い散歩やおやつ、家族の雑談で空気を入れ替えます。
短時間の気分転換/オンラインや手紙でつながる
友だちとはLINEで交流を続けました。
長電話はしない、でも「つながっている」感じは切らさない。
この温度感がちょうどよかったです。
体調と生活管理
食事で気をつけたこと
生ものは控え、体を冷やすものも減らしました。
温かい汁物、消化のよいおかず、果物を少し。
特別なメニューではなく、ふつうの家庭食を丁寧に作る意識です。
生ものを控える/体を冷やさない/栄養バランスを意識
受験は体が資本。
食事は「安心して勉強できる土台」と考えました。
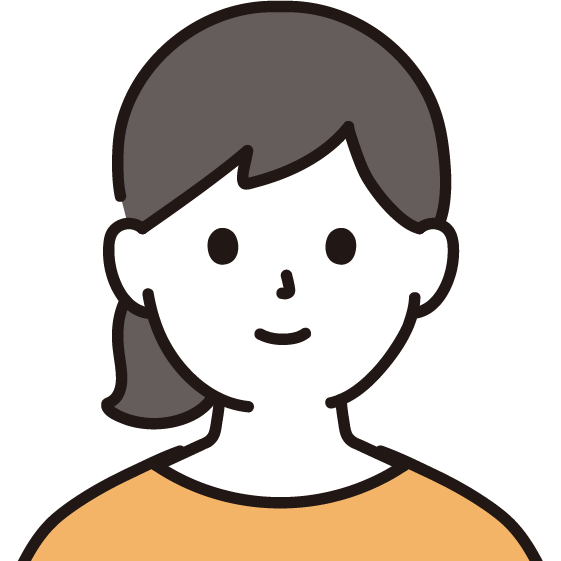
今考えると、『うどん』ばかり食卓に並んでいたような・・。献立を考える余裕もなくなるので、あらかじめ『献立表』を準備しておくのがいいかもしれません。
睡眠・入浴・環境
夜更かしはしませんでした。
お風呂でしっかり温まり、部屋は加湿。
よく眠れた日は、勉強の質も上がります。
夜ふかしをしない/お風呂で温める/加湿と換気
朝起きて寒いと感じたら、息子が好きな野菜スープやレモネードをよく作りました。
小さな習慣が体調を守ってくれます。
親の働き方とサポート(当時はフル出勤・帰宅22時あり)
当時はフル出勤、帰宅は22時。
私は仕事を続けながらの受験期でした。
今は在宅勤務ですが、当時は毎日出社。
帰りが22時ごろになる日も少なくありません。
家にいない時間が長いぶん、「短い段取り」と「見える化」で回しました。
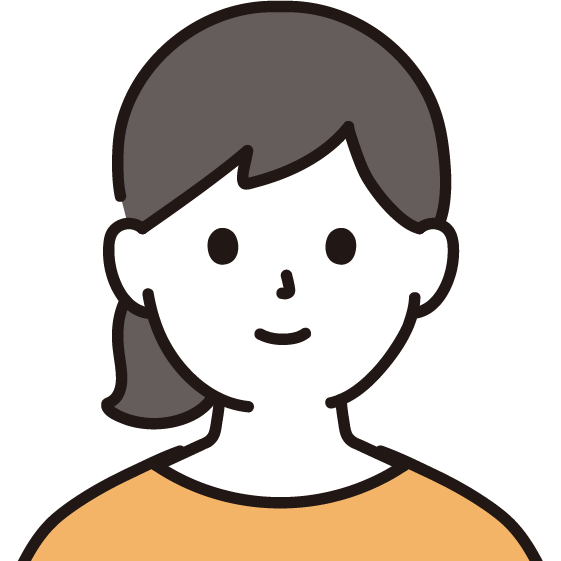
この時期の職場は、数年に1度レベルの繁忙期。受験がなくてもしんどい状態だったため、おばあちゃんにサポートをお願いしました。
朝の準備/夜のふり返り
朝は紙1枚に「今日やること5つ」を書いてテーブルへ。
問題集もコピーして準備。
タイマーの時間も横にメモ。
夜は帰宅後に解答のチェック。
すでに見直しまで完了しているので、間違えた箇所のみ知識の定着を口頭チェック。
年1回の10日連休+有給で、2週間の集中期間を作る
職場には年に1回、10日間の長期休暇がありました。
そこへ有給を重ねて約2週間の学習ブロックに。
家事は前倒し・時短に切り替え、勉強と休息のリズムを先に決めて入りました。
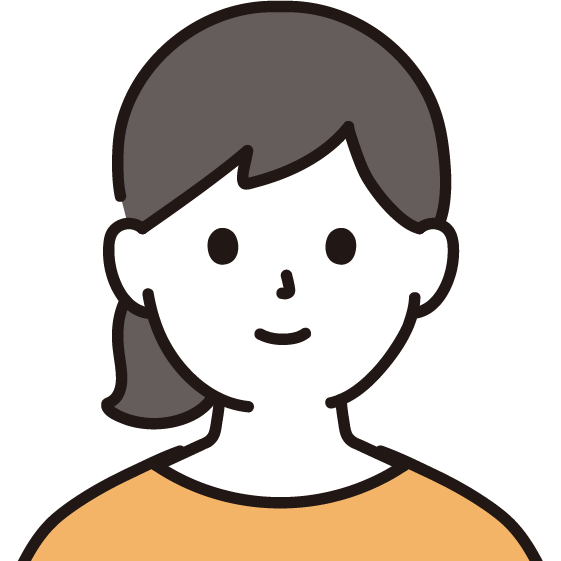
職場には迷惑をかけてしまって、申し訳ない気持ちでいっぱいでしたが、『子どものサポートだけ考えて!』と声をかけてくれる同僚も多く、本当に感謝の気持ちでいっぱいでした。
「山は過去問/谷は回復日」で波をつくる
1週目は過去問で全体像、2週目は弱点つぶし。
真ん中に1日だけ「完全オフ」を入れて体と心を休める。
予定表に最初から休息日を書いておくと、息切れせずに走り切れました。
面接なしの学校で優先したこと
正確さとスピードを上げる
面接がないぶん、筆記の点で勝つしかありません。
計算と基本問題の取りこぼしをゼロに近づけました。
とにかく数をこなすを意識しました。毎日10分×2回をコツコツと。良問のおすすめ問題集⇒〖中学受験〗計算力アップの決定版|『でる順過去問 計算 合格への920問』特徴・効果・口コミ【正直レビュー】
見切りの基準を決め、落とさない問題を確実に取る
「3分考えて進まなければ飛ばす」「最後に戻る」。
見切りのルールを先に決めて、練習でも徹底しました。
配点を意識した学習
配点が高い大問は優先して対策。
時間の使い方も配点に合わせました。
得点源を確保して、合格点に届く形を作ります。
計算・選択問題の精度を高める
選択問題はケアレスミスが命取り。
見直しの順番も決めて、最後まで点を取りにいきました。
リスクと対策
友だち関係
急に消えると心配されます。
休む前に短く事情を共有し、休み明けは一番にあいさつ。
これで十分でした。
事前のひとことと休み明けのフォロー
「頑張ってたんだね」と言ってもらえて、息子の表情も明るくなりました。
体力低下
座りっぱなしは禁物。
朝と夕方に軽い運動を入れました。
数分でも血のめぐりが変わります。
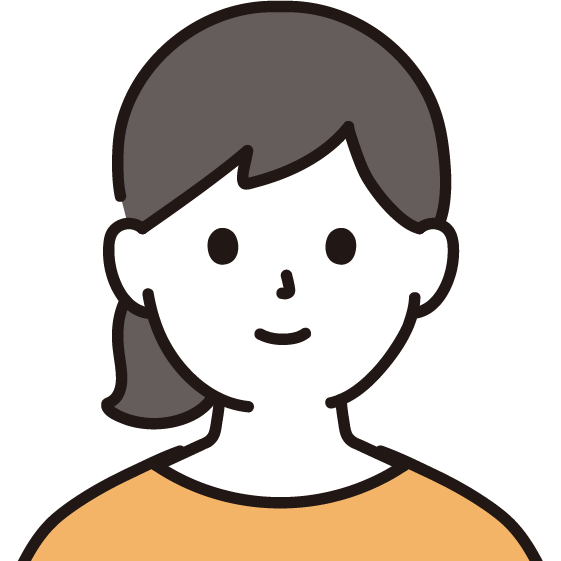
軽い運動といっても、ほぼ親子でじゃれあっているようなものでした。アレンジ激強のラジオ体操したり、ウルトラマンvsハム太郎ごっこ・・というよくわからないこともしました。笑”
休み明けのリスタート
宿題・連絡のリカバリー
宿題は出す日と量を先生と相談。
いっぺんに出さず、数日に分けて提出しました。
連絡物は保護者がまとめて確認しました。
期限と優先度を整理する
「今週中に必要なもの」「来週でも大丈夫なもの」を分けるだけで、負担が軽くなります。
先生へのお礼
長く休むと、先生にもご負担がかかります。
再開の日に短くお礼と近況を伝えました。
気持ちが伝われば十分です。
短いお礼と近況の報告
「ご配慮ありがとうございました。無事に受験を終えました」。
この一言で空気がやわらぎました。
生活リズムを戻す
受験モードから学校モードへ。
起床・就寝、朝ごはん、身じたく。
この三つを元に戻すだけで、日常は動き出します。
起床・就寝をふだんに戻す
1〜2日で戻らなくても大丈夫。
あせらず、いつもの時計に合わせるだけでOKです。
よくある質問(欠席・学校との関係など)
欠席の扱いはどうなる?
欠席の数え方や出席停止の扱いは学校ごとに違います。
まずは学年便りや校則を確認し、分からない点は早めに担任の先生へ相談すると安心です。
学校のルールを事前に確認する
決まりを知っていれば、余計な心配が減ります。
学校行事は出たほうがいい?
卒業に関わる大事な行事は、できれば参加を。
体調や学習の進み具合と相談し、出る行事は先に決めておくと迷いません。
重要度で選び、出る行事は決めておく
「これは出る」「これは休む」を家族で決め、先生にも伝えておくとスムーズです。
どのくらい休むのが目安?
目安は家庭の事情と学校の状況で変わります。
わが家は「12月受験」のため「11月まるっと休む」を選びました。
期間よりも、目的と計画があるかが大切です。
目的と学校の状況で決める
迷ったら短めに始め、必要なら延ばすほうが安全です。
まとめ|「中学受験で学校を休む」判断チェック
目的・期間・計画は決まっているか
「なぜ休むのか」「いつまで休むのか」「毎日何をやるのか」。
この三つが決まらないのに学校を休んでも、だらけてしまう可能性があります。
しっかりと目的を持ちましょう。
志望校対策の道筋は見えているか
過去問10年→原因分析→単元演習(『自由自在』『でる順過去問』)の流れが回るなら、合格点に近づけます。
学校と家族の合意は取れているか
学校への連絡、友だちへの一言、家族の役割分担。
先に整えておくと、静かに学びに集中できます。