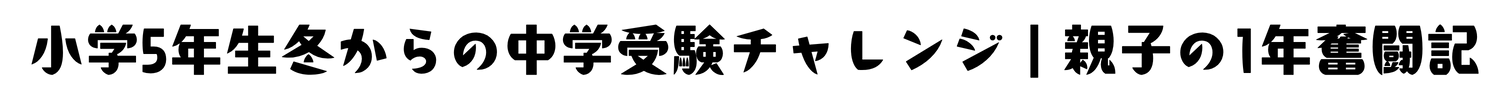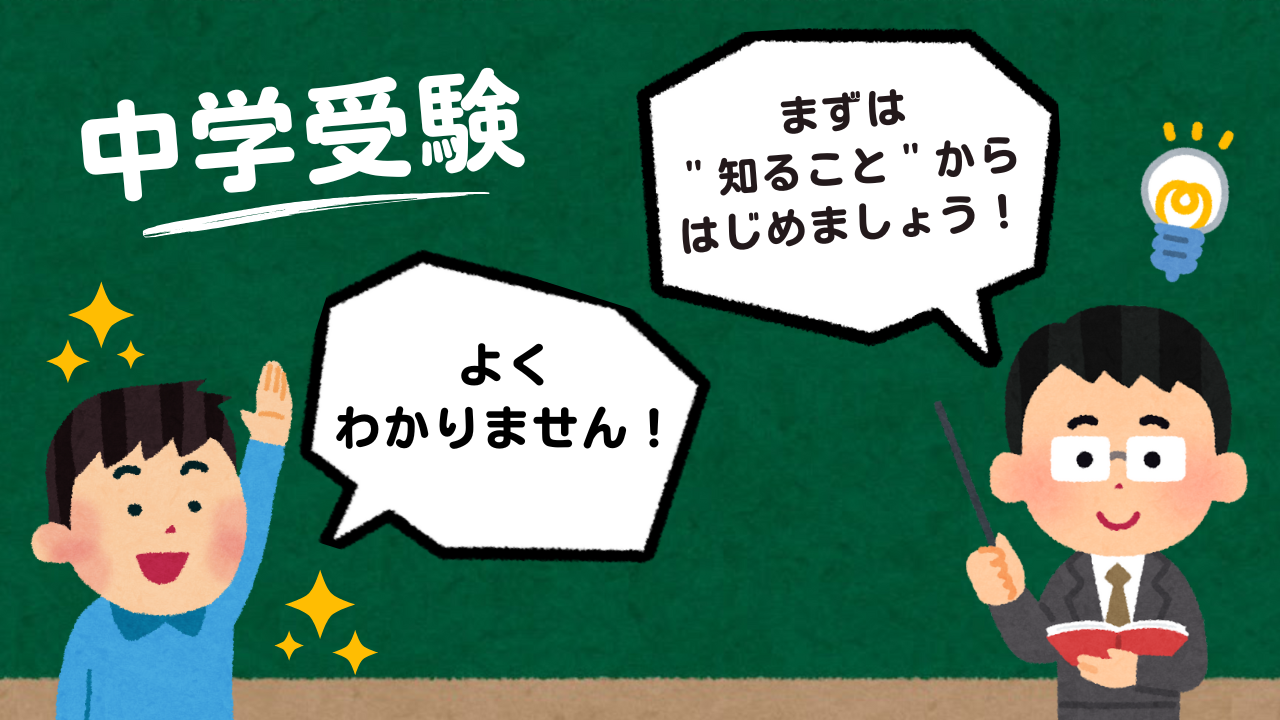「何校受けたら安心なんだろう?」
中学受験を考えはじめた時、まず悩んだのがこの「何校受けるんだろう問題」でした。
こんにちは、ぽんままです。
我が家では、小5の冬に中学受験を決意。
そこから1年ちょっとで受験本番を迎え、中堅上位校に合格しました。
今回は、実際にどれくらいの学校を受験したのか、なぜその数にしたのか、当日のトラブルやよかった点など、リアルな体験談をお届けします。
※あくまで我が家の場合です。
全員にあたはまるわけではありませんが、何かの参考になればうれしいです!
我が家が受験したのは「◯校」だけ!
結論から言うと、受験したのは1校だけです。
ちょっと驚かれるかもしれませんが、家庭の事情もあってこの選択に落ち着きました。
通学時間・学費・本人の希望をすり合わせた結果、「この学校に行けるなら悔いなし!」と思えた学校1本に絞りました。
もちろん、不合格なら公立中という覚悟のうえです。
リスクはありますが、我が家にはこのスタイルが合っていました。
一般的な「受験校数の目安」は?
塾の先生からは、「3〜5校が一般的」と教わりました。
・第1志望(チャレンジ校)
・第2志望(実力相応)
・第3志望(安全校)
この3段階で考えることが多いそうです。
さらに、学校によっては1月校(関西や地方など)の受験を「練習用」に加えるご家庭もあります。
受験校をどう決めた?
我が家が大切にしたのは、「通えるか」と「本人の気持ち」でした。(あと、複数校もの受験料がきつい!という母のお財布事情・・・)
母子家庭なので、通学に1時間以上かかる学校は難しい。
また、息子が人見知りだったので、無理にたくさん受けさせるとメンタルがもたないと思いました。
そのため、あれこれ受けさせずに、本人が「ここがいい!」と思えた学校だけに集中する戦略を取りました。
実際に使った教材と受験対策
1本勝負だったので、演習量をとにかく重視しました。
市販で売っている『口コミ評価の高い教材』を総ざらい
塾では限界があると感じ、市販で評判のいい問題集を片っ端から買って取り組みました。
「下剋上算数」「塾技」「自由自在」など、SNSやブログで名前をよく見る教材を中心に、分野ごとに幅広く対策しました。
ほかにもおすすめ教材を紹介しています! ⇒教材レビューを見る
特徴:分野ごとにレベルや形式が違うので、息子の弱点を洗い出しやすかった。
使い方:朝は計算系、夜は読解や理科・社会の暗記系と、時間帯に合わせて使い分け。
効果:とにかく問題に多く触れることで「初見」に強くなった実感がありました。
志望校の過去問は『10年分×繰り返し』
市販の過去問集で、志望校の問題を10年分入手。
1冊を3〜4回は繰り返し、本番形式で演習しました。
特徴:傾向がはっきりしている学校だったので、繰り返すことで「出そうな問題の雰囲気」がつかめた。
使い方:1回目は時間無制限で内容を理解。2回目以降は制限時間を設けて本番モードで実施。
効果:本番当日は「想定内」の問題が多く、安心して臨めたとのことでした。
1校受験のメリット・デメリット
◎メリット:
・対策を1校に絞れるので効率がいい
・受験日程に余裕があり、体調管理もしやすい
・本人の気持ちがぶれない
△デメリット:
・万が一落ちたら公立進学
・本番の1回にすべてがかかるプレッシャー
・塾のカリキュラムが複数校受験を前提としていると合わないことも
まとめ:何校受けるかは「家庭のスタイル」による!
中学受験は、何校受けるのが正解か…というより、「その家庭にとってベストな形」が大切だと感じました。
我が家のように1校勝負もアリだし、不安があれば複数校を受けるのも安心材料になると思います。
大切なのは、「お子さんと一緒に考えること」と、「通学や家庭の事情も含めた現実的な判断」。
この記事が、受験校数に悩むご家庭の参考になればうれしいです。