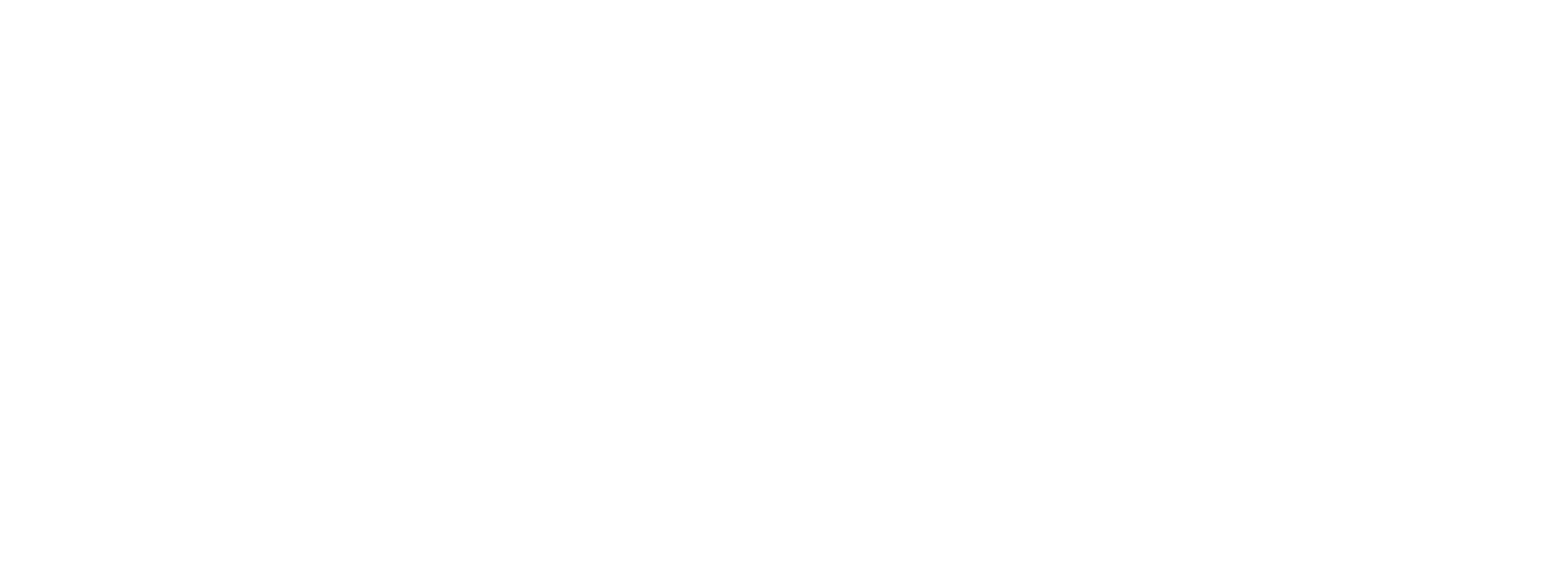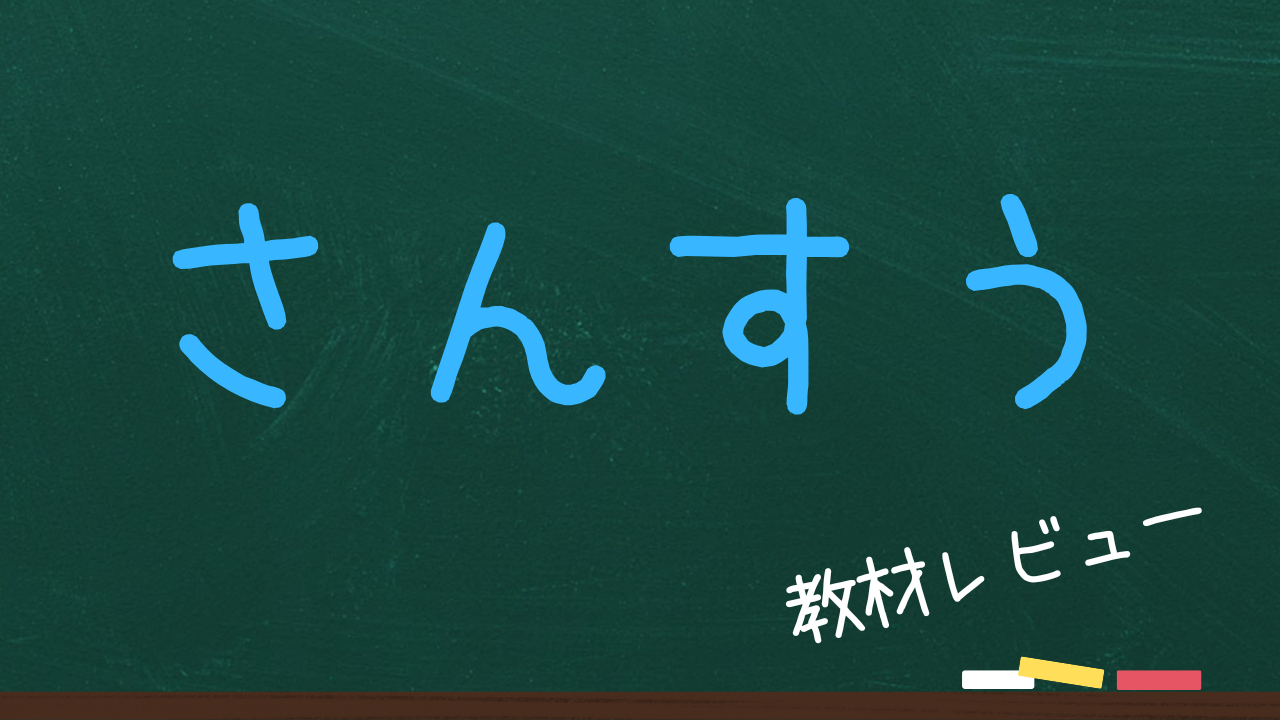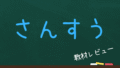「公式は覚えたのに、速さの問題になると手が止まる…」そんなお子さんは少なくありません。
わが家も同じでしたが、図や表で状況を“目で見る”ようになってから、解く順番が自然と整い、自信が戻ってきました。
この記事では、忙しい家庭でも回しやすい本書の良さと、旅人算・通過算・流水算に効く学習の流れを、母の目線でていねいにお伝えします。
『集中レッスン 速さ』はどんな教材?【概要と特徴】
状況を見える化する紙面づくり
速さ・時間・距離の関係を、線分図やダイヤグラムで整理する導線がしっかりしています。
文字式より先に“図で理解”できるので、式を立てる前の迷いが減りました。
小さなステップで自動化へつなぐ構成
例題で型を確認し、基本→練習→実戦の順に負荷を少しずつ上げます。
短時間でも区切りよく進められる分量で、平日の学習に組み込みやすいのが助かりました。
旅人算・通過算・流水算を横断する視点
単元ごとのコツを別々に暗記させるのではなく、「相対速度」「一定時間あたりの進み」を軸に横断的に考える作法が身につきます。
応用問題へスムーズに橋渡しできます。
なぜ「速さ」で得点差がつくのか【本番で強くなる理由】
時間配分の起点になる分野
速さの設問は序盤~中盤に配置されることが多く、ここで手早く正確に解けると全体のペースが整います。
逆に手間取ると見直し時間が削られ、後半に響きます。
計算と読解の“橋渡し”が問われる
文章から条件を抜き出し、図に落として式へと渡す流れが鍵です。
どれか一つでも弱いと解答まで届きません。流れが整うと得点が安定します。
相対速度で一気に視界が開く
「離れる・近づく・追いつく」を相対速度で捉え直すと、旅人算だけでなく通過算・流水算も共通の型で処理できます。
思考の再利用ができるのが強みです。
この教材で得られる効果とメリット
図から式へ、式から検算への一筆書き
図で方針を決め、最短の式に落とし、単位とオーダーで検算する習慣が自然に身につきます。
本番での再現性が高まりました。
単位変換と比の感覚が安定する
km/hとm/s、分と時間など、速さ特有の単位変換を繰り返し扱うため、換算の迷いが減ります。
比を使った処理もスムーズになります。
応用問題での“手戻り”が減る
状況整理の型が固まると、複雑な設定でも試行錯誤が減ります。
むやみに式を増やさず、最短の道筋で解答に到達できます。
実際に使ってみた感想【体験談】
朝に方針、夜に練習のリズムが合う
朝は例題を一緒に読み、線分図まで作って方針を共有。
夜は子どもが自力で練習を解く流れが定着し、親の関与は最小限でも進むようになりました。
「速さ=図から」の合言葉で迷いが消える
公式から入ると迷子になりがちでしたが、「まず図」の習慣に切り替えてから、計算のやり直しが激減。
正答率とスピードが同時に上がりました。
通過算が得意単元に変わった
列車の長さ・橋の長さ・入れ替わりなど、混乱しやすい要素も、図で“通過する距離”を先に固定する癖がつき、取り組むたびに手が軽くなりました。
口コミ・レビューで見かけた評価の傾向
見通しの良さが支持される
状況整理の導線がわかりやすく、「子どもが自分から図を描くようになった」という声が目立ちます。
家庭学習の主軸にしやすいという感想も多いです。
導入は基礎の一歩手前からが安心
単位変換や比が弱いとつまずくことがあるため、導入期はやさしい例題で成功体験を積み、並行して基礎の復習を入れると定着が早まります。
性格に合わせたペース調整が鍵
テンポよく進めたい子には相性が良く、じっくり派の子には復習日をこまめに挟むのが効果的。
量より質を意識すると安定します。
効果的な使い方と学習のコツ
学習前に「何を図にするか」を宣言する
図を作る前に「距離・時間・速さ、どれを基準に考えるか」を声に出して決めましょう。
最初の1分で方針を固めることで、迷わず解けます。
週一の“通し演習”で時間感覚を養う
旅人算・通過算・流水算を混ぜ、時間を測って連続で解く日を作ります。
見直し込みの呼吸が体に入り、本番の配点と時間配分に強くなります。
単位・オーダーの口頭チェックを習慣化
答えを書く前に、単位と桁を口に出して確認します。
kmとm、分と時間の取り違えを、その場で止められるようになります。
間違った使い方をすると効果半減!やってはいけない学習法
公式の丸暗記から入ってしまう
「み・は・じ」だけで押し切ろうとすると、条件が複雑な問題で崩れます。
必ず図→式→検算の順で流れを固定しましょう。
図を描かずに頭で処理する
速さは情報量が多く、頭の中だけでは抜け漏れが出ます。
線分図やダイヤで、見える形に落とすことが最短の近道です。
難度を急に上げて成功体験を切らす
成功の連鎖が自信を支えます。
基本→練習→実戦の順を崩さず、三歩進んだら一歩戻るリズムで復習を挟みましょう。
よくあるつまずきと克服法
速さ・時間・距離の混同
図に「求めたい量」を赤で、与えられた量を黒で書き分けます。
色や記号で役割を分けると、式の置き間違いが減ります。
単位変換ミス
換算は計算の前に必ず行い、問題用紙の余白に換算表を作ります。
m/s⇔km/hの往復を口に出して確認する習慣が効果的です。
通過算の“距離”の取り違え
「通過距離=列車の長さ+相手の長さ」を先に確定し、相対速度で割る手順を固定します。
距離が決まれば計算が一気に軽くなります。
速さは、図で状況を整えれば必ず味方になります。
完璧を求めすぎず、今日の短い一歩を丁寧に積み上げていきましょう。
お子さんの歩幅に合わせて、図から式へ、式から検算へ。
この流れが定着したとき、点数だけでなく学ぶ自信も育っているはずです。