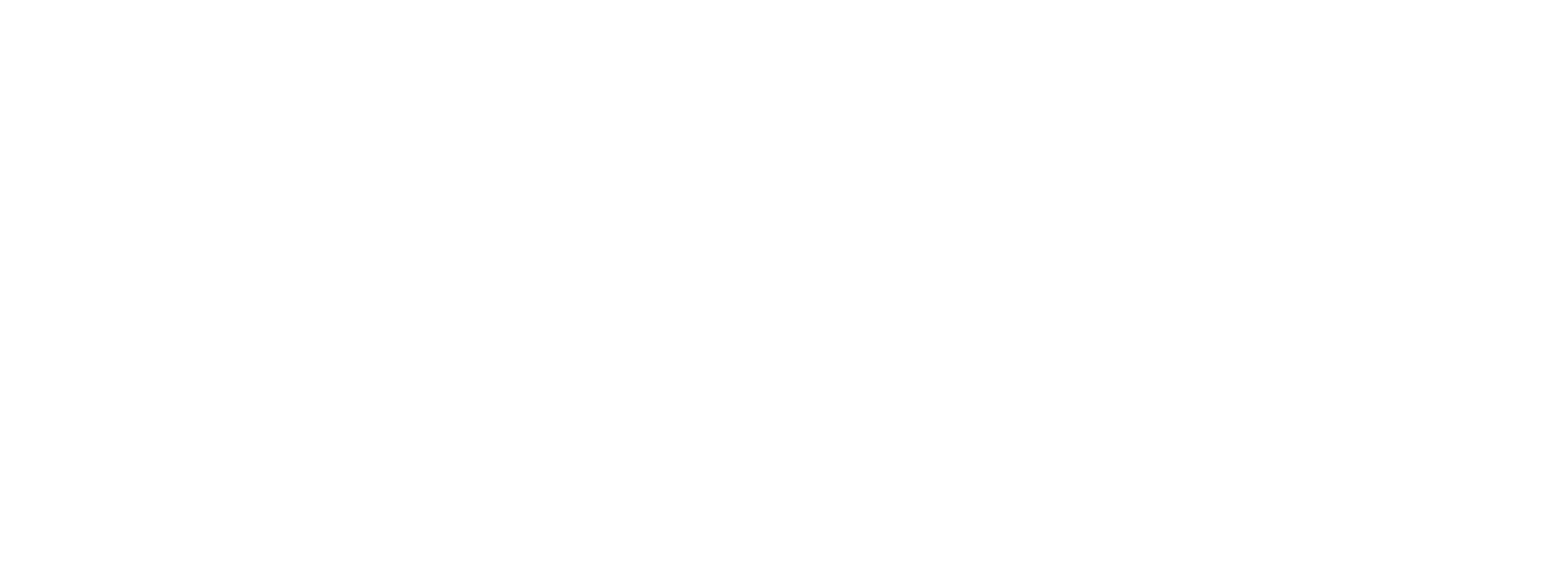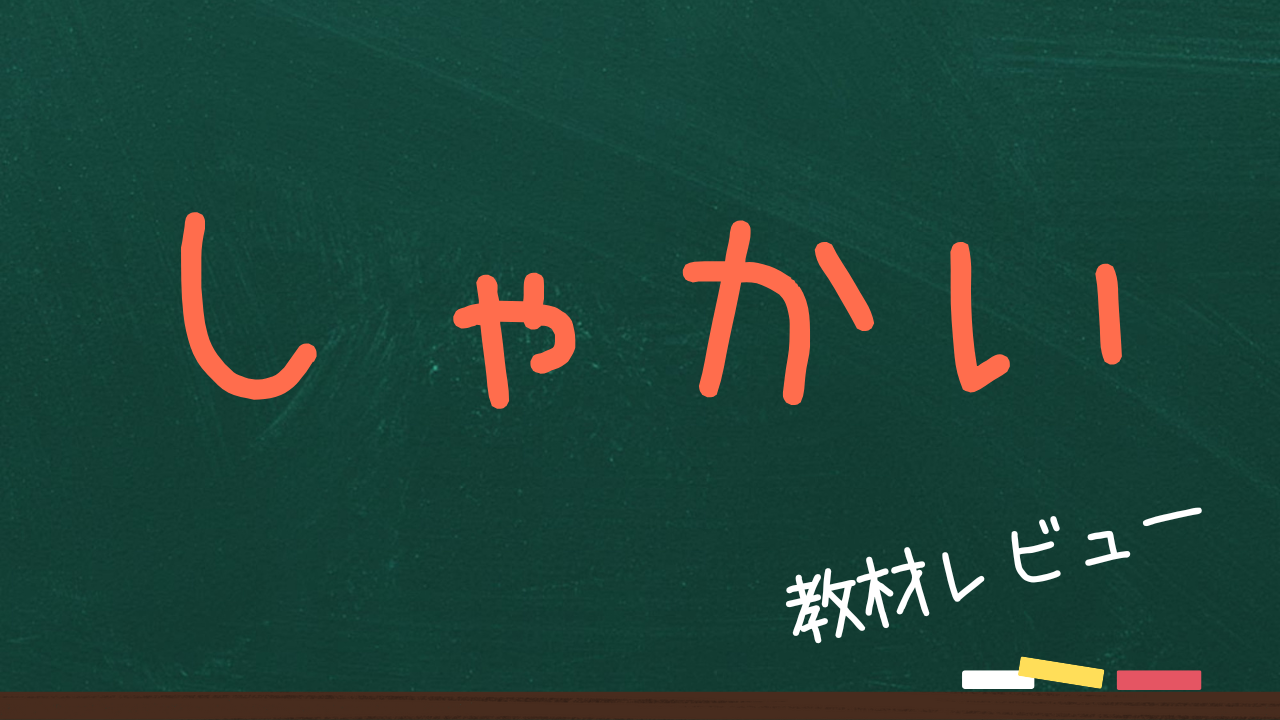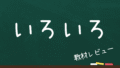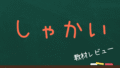「社会は覚えてもすぐ抜ける…」「限られた時間でどこから手をつければ?」という悩みに、この一冊は明確に答えてくれます。
入試傾向を分析して“出る順”に並べた1008問を、3ステップ構成でテンポよく回せるのが最大の魅力。
口コミでも「短時間で総確認に向く」「視認性が高く取り組みやすい」という声が目立ちます。
本記事では、信頼できる情報と実際の評判をもとに、合格へつながる具体的な回し方まで整理しました。
どんな教材?──特徴・レベル感・到達点
収録形式と基本データ
旺文社『中学入試 でる順過去問 社会 合格への1008問』は、B5判176ページ(2色・一部カラー)+別冊解答40ページ。
近年の入試を分析し、頻出度の高い問題を「でる順」で配置しています。
各単元は「まとめ → 重要用語チェック → 入試問題にチャレンジ」の3ステップ構成で、巻頭には入試傾向と対策の解説も収録。
対象は小5~小6(小3~小4も可)とされています。
学習レベルと想定ユースケース
レベル表記は「基礎~標準~応用」。
用語確認から入試頻出の演習まで段階的に進められるため、知識の最終整理や模試前の総点検にフィットします。
確認用として最適で、身につけば必要最低限の知識は広く網羅できます。
単元構成(地理/歴史/政治・国際)
地理は「日本の国土・産業・世界の姿・地図の見方」など、歴史は「旧石器~現代」まで、政治・国際は「三権・憲法・国際関係・地方自治」などを頻出順で展開。
資料読解・テーマ史の番外編もあり、実戦的なカバー範囲です。
効果が出る使い方──1日の回し方・週次プラン・単元サイクル
小5:インプット期は「短時間×高頻度」
用語チェックを軸に、1回10~20分で小分けに反復。頻出順の並びを活かし、得点に直結する領域から押さえます。
短時間でも「まとめ→用語→入試問題」の順で手を動かすと定着が上がります。
小6前半:弱点つぶしと頻出テーマ集中
周回表を作り、間違えた設問だけ翌日・3日後・1週間後で再挑戦する“間隔復習”。
「重要」「差がつく」「思考力」などの目印を使い、優先度をつけて回転を速めます。
小6夏~秋:過去問と併走する総点検
学校別過去問で見えた穴を、本書の該当単元へ戻ってピンポイント復習。
レビューでも「直前期の総確認に向く」「短時間で復習できた」との声があり、直前フェーズの相棒としての相性が高い教材です。
口コミ・評判の傾向──良い点/気になる点/合う家庭像
良い口コミ:短時間で回せる・見やすい
「直前期の総確認にちょうどいい」「短時間で効率的に復習できた」といった声が複数。
紙面は多色で見やすく、項目がコンパクトに整理されている点も支持されています。
気になる点:易しめ/最新版チェックが必要
「練習レベルが中心で、仕上げ後はステップアップが必要」という指摘や、社会は内容更新があるため保護者の目配りが必要という意見も。
合う家庭像:頻出重視・時間が限られるご家庭
頻出順の並びと3ステップ構成は、時間が限られる家庭学習と相性が良好。
「効率重視」「まずは基礎~標準を盤石に」という戦略にマッチします。
教育系サイトや塾ブログでも“反復用・効率重視”の評価が見られます。
一問一答の暗記を“忘れにくくする”運用法
間隔復習×周回表で「できない」を可視化
間違えた問題に印と日付を残し、翌日→3日→1週間のサイクルで再挑戦。
正答したら印を薄く、2回以上連続正答で卒業に。
短いサイクルで回すことで、知識の維持コストを抑えられます。
音読・タイマー・自作プリントの併用
用語定義は声に出し、60~90秒のタイマーでテンポを固定。
忘れやすい表や年号は自作プリントに抜き出して朝学習に回すと、定着のムラを減らせます。
朝10分・夜20分のミニマル設計
朝は用語チェック、夜は「まとめ→入試問題」を1ブロック。
1日合計30分でも、頻出順の利点で“効く学習”になりやすいのが本書の強みです。
単元別の攻略ポイント(地理/歴史/公民)
地理:資料読み取りを最優先
統計・グラフ・地図記号など、資料問題の型を押さえつつ、頻出単元(国土・産業・世界の姿など)を優先的に周回。
章立てに沿えば“でる順”で無駄なく回せます。
歴史:年表×人物×出来事の三点リンク
各時代の出来事を年表に落とし、主要人物や制度と関連づけて覚えると、記述や資料読解にも転用しやすくなります。
頻出の時代から着手すると効率的です。
公民:用語は定義まで言える形で
「国会・内閣・裁判所」「憲法」「地方自治」などは、語の意味+具体例まで押さえると取りこぼしが減少。
巻頭の傾向解説も合わせて確認しましょう。
併用したい教材と役割分担
知識の穴埋め:図解・資料アイテム
資料・ポスター・暗記カード系は、弱点の“見える化”に有効。
暗記アイテムを併用することで、知識の取りこぼしを減らせます。
記述・論述の底上げ:答え方トレーニング
本書で用語・頻出知識を固めたら、別冊や他書で記述演習を追加すると“説明できる力”に接続しやすくなります。
志望校の傾向に合わせて負荷調整を。
過去問への橋渡し:単元別リカバリー
過去問で落とした設問は、本書の該当単元へ戻って即リカバリー。
「基礎~標準の確認用として最適」という評価と相性がよく、直前期の総点検にも使いやすいです。
親の丸つけ・進捗管理を最小化する運用術
チェックリストと色分けで二度手間を削減
各単元の達成度を「未着手/要復習/定着」の3色で管理。
誤答番号に付箋を貼り、翌日の復習対象を可視化すると丸つけの手戻りが減ります。
100問ごとの小さなごほうび
1008問は長距離走。100問クリアごとにスタンプや小さなごほうびを設定し、モチベーションを切らさない仕組みに。
朝・夜の分担ルール
朝は親が用語チェック、夜は子が演習→親が答え合わせ、と役割を分けると負担が一定に。
家庭学習で続けやすい体制を作れます。
まとめ
-
頻出度に基づく“でる順”と〈まとめ→用語→入試問題〉の三段構成で、1008問を短時間で周回できるのが最大の強みで、直前期の総確認と弱点把握に向く。
-
対象は小5後半〜小6の基礎〜標準中心で、模試前の点検や仕上げに最適だが、社会は改訂が多いため版や最新情報の確認を忘れずに進めたい。
-
朝は用語チェック、夜は演習の30分設計にし、間隔復習と周回表で誤答のみ再挑戦、過去問と併走して穴を即時リカバリーし学習を習慣化する。
-
頻出重視で効率よく積み上げたい家庭や中堅校志望の子に相性が良く、知識定着後は記述や資料読解を別教材で補強すると得点力が伸びやすい。
-
親の丸つけ負担は色分けチェックと付箋で最小化し、100問ごとの小さなごほうびや朝夜の分担ルールで継続性を高め、学習を無理なく継続する。
よくある質問と回答
Q1.いつから始めるのが最適ですか?
開始時期は小5後半〜小6初期が扱いやすいですが、学年よりも“毎日触れる密度”が重要です。模試や学校行事から逆算し、直近2回の模試の間に1周を収めて、無理のない回転速度を測りましょう。
Q2.難関校志望でもこの教材は使えますか?
難関校志望でも無駄にはなりません。頻出知識の土台づくりに使い、並行して資料読み取り・記述演習・時事の横断学習を追加すると、得点源が多様化します。誤答は「なぜ」を言語化してノート化を。
Q3.他教科と両立させるコツはありますか?
社会は短時間で“積み上がり”を実感しやすい科目です。算数や国語の重たい課題の合間に10〜15分のミニセッションを挟み、週末だけは復習のまとまった時間を確保。日ごとの役割と曜日テーマを固定すると続きます。
Q4.デジタルツールと併用すると良い方法は?
紙中心でもデジタル補助は有効です。誤答ページを写真で保存し、表計算で進捗を自動集計、読み上げアプリに用語を録音して移動時間に耳で確認。チェックボックス付きの進捗表をホーム画面に置くと迷いません。
Q5.子どもが飽きたときの立て直し方は?
飽きたら“学びの形”を変えます。単元ごとにビンゴ表を作り、達成マスをめくる仕掛けにする、親子で出題者役を交代する、同じ範囲を別の教材で30問だけ試すなど、刺激を入れ替えて再起動を図りましょう。