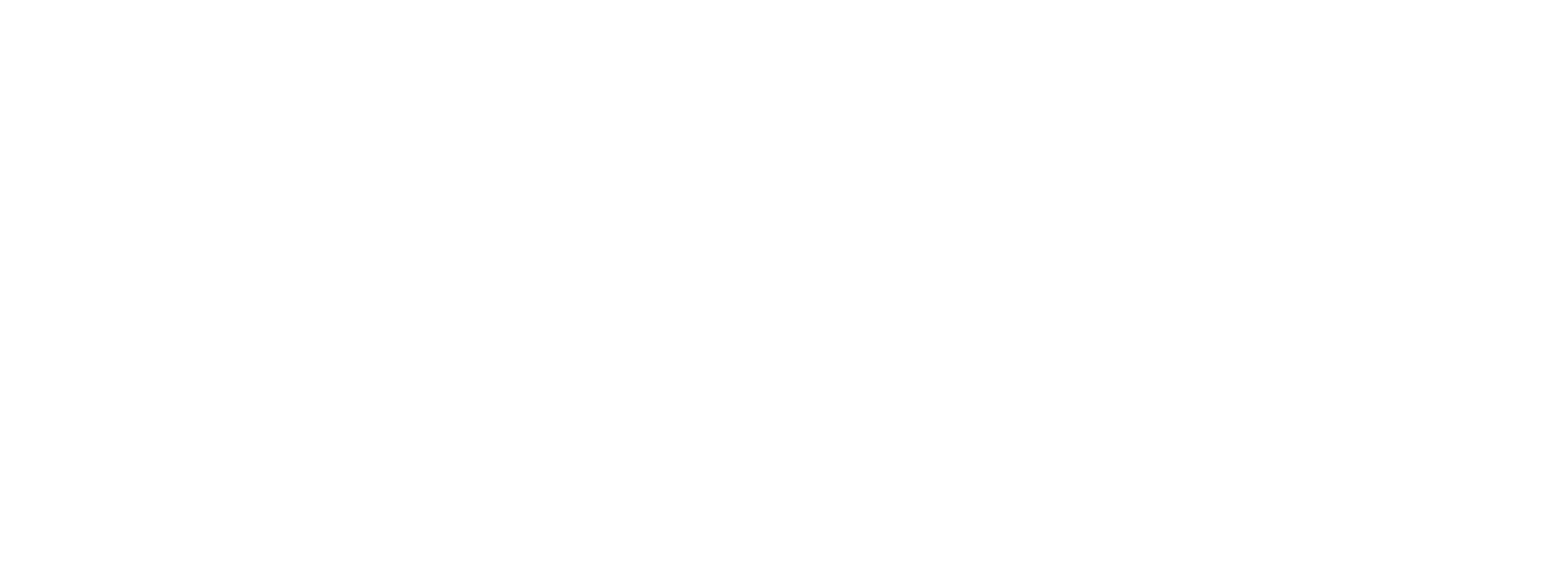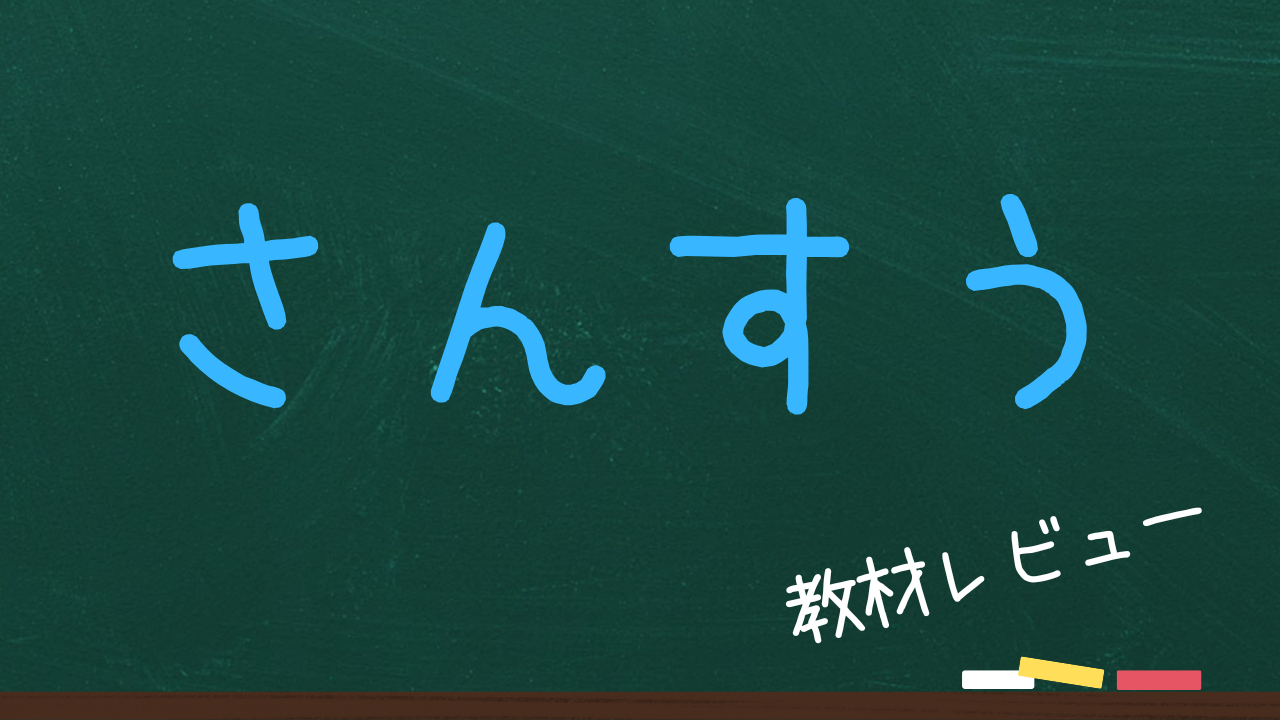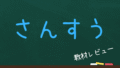図形の問題を見ると、うちの子はいつも眉間にシワ……。
でも、ある一冊に出会ってから、図の見え方が少しずつ変わりました。
私は仕事を終えると夜の10時過ぎ、塾は最小限、頼れるのは市販教材と家庭学習だけ。
それでも「やり方」をつかめば、図形は前に進めます。
この記事では『中学受験 すらすら解ける魔法ワザ 算数・図形問題』を、母の目線で正直にご紹介。
評判や使い方、わが家の工夫まで、明日の学習から役立つヒントをまとめます。
この教材はどんな本?
図形を「手順」でほどく考え方が身につく
角度・面積・相似・立体の切断といった出題の柱を、「見る→分ける→置き換える」という順番で考える流れに沿って解説してくれます。
公式を暗記して当てはめるのではなく、どこを基準に見れば道が開けるのかを、紙面のガイドで丁寧に示してくれるのが好印象です。
図の上に補助線が入る前後の比較がわかりやすく、子どもが「なぜ今この線?」を言葉で説明できるようになりました。
例題→手を動かす練習→仕上げの確認の三段構成
見開きの中に、導入の例題とポイント、続けてすぐに解ける練習、最後に似たタイプで確かめる流れがまとまっています。
一度座って机に向かえば、ダラダラせずに一単元を気持ちよく終えられるボリュームで、家庭学習のリズムづくりにぴったりです。
親が横で見守る場合も、どこで声をかけると良いかが紙面から読み取りやすく、付き添いの負担が軽く感じました。
レベル感は「基礎〜標準を確実に」。応用への土台作りに
いきなり難問を解くというより、頻出の「型」を確実に拾い上げる設計です。
基礎がほころんでいると応用で必ずつまずくので、 まずはこの本で視点の置き方と図のさばき方を固める——そんな位置づけが合います。
塾なし・最小限でも取り組みやすい厚みです。
口コミ・レビューから見えた評判
「図のどこを見るか」が言語化されていて親子で共有しやすい
感想で多かったのは、解き方の理由が言葉になっている点の評価でした。
子どもが「中心角だから」「相似が作れるから」と説明できるようになると、 自己採点ややり直しの質が上がります。
家庭学習では、この「言葉で説明できる」ことが伸びのカギになります。
補助線の入れ方や面積比の扱いが丁寧で、つまずきが減る
補助線は魔法の一本ではなく、目的がある線——その感覚を紙面で体験できます。
特に面積比・相似比の扱いは、 図を分け直して考える練習が段階的に用意されており、「なんとなく」で進めない作りです。
ここが続けやすさにつながっていました。
一方で「もっと難しい演習が欲しい」という声も
標準レベルを固める構成ゆえに、志望校の過去問に近い難度をもっと解きたいご家庭には、仕上げ用の演習を別で足すのが良さそうです。
わが家は、週末だけ応用問題集を1〜2題添える形でバランスをとりました。
土台ができると、応用でも迷子になりにくくなります。
実際に使ってみた感想(ぽんまま体験談)
「図が怖くない」に変わった最初の一週間
最初の一週間は、1日1見開きだけと決めて取り組みました。
時間は15〜20分、解けないときは無理に粘らず翌日に回します。
「今日はどこを見る回?」と声をかけると、子どもは基準点を自分で探すように。
ここで小さな成功体験が積み上がりました。
夜10時過ぎに帰宅しても回せた家庭学習ルーティン
私が帰宅する前に子どもが例題と練習まで進め、帰宅後に10分だけ口頭で解説してもらう流れにしました。
説明してもらうと理解の穴が見えますし、親の負担は最小に。
コピーした問題を朝に用意しておくと、机に座るまでがスムーズでした。
中堅校狙いなら「得点の土台作り」にドンピシャ
最難関突破の奇跡の一打ではなく、合格点に確実に近づくための安打を積み上げる教材だと感じました。
模試の図形分野でケアレスミスが減り、得点が安定。
気持ちの揺れが小さくなるのは、親子ともに大きなメリットでした。
効果的な使い方——わが家のコツ
学習前に「基準を声に出す」1分間
問題を開いたら、距離・時間・速さのように、図形でも「どこを基準に見るか」を声に出して宣言します。
角なら中心と円周、相似なら対応辺、立体なら断面の向き——この1分で視点が定まり、迷いが減りました。
間違いは「型ノート」に貯金する
ただのやり直しではなく、つまずいた原因を「型」にして小さなノートに一行でまとめました。
例えば「角の和で攻める前に相似の当てはめを探す」など、次に開いたときにすぐ効く言葉で残すのがコツです。
週末に3分だけ見返すだけでも、定着のスピードが違います。
仕上げは「類題ワンモア」で記憶を固める
当日の見開きを終えたら、翌日に同タイプの短い問題を一題だけ。
忘れかけのタイミングで手を動かすと、解法が自分のものになります。
忙しい日は、図だけ見て「今日はどこを見る?」と口だけでもOK。
続けることを最優先にしました。
どんなご家庭におすすめ?
塾は最小限、家庭学習で力をつけたい
限られた時間と予算のなかでも、要点を押さえた紙面設計で一歩ずつ進めます。
親の付き添いがなくても回しやすく、 帰宅が遅い日でも学習のペースを崩しにくいのが助かりました。
図形への苦手意識を「見方のコツ」でほどきたい
苦手なのは才能がないからじゃなくて、見方や考え方の練習が足りないだけ。
補助線や比の扱いを理由とともに身につけたい子に向いています。
「解けた理由」を言葉にできるようになるので、模試のやり直しの質が上がります。
親も一緒に解法の筋道を知りたい
紙面のガイドが丁寧なので、親も短時間で要点を把握できます。
夜の数分で子どもの説明を聞く—— そのスタイルでも十分にサポートできました。
明日の勉強から変えられる、小さな一歩
まずは一見開き、視点を声に出すところから
立派な計画は要りません。
今日から一見開き、基準を声に出す1分で、図形の見え方は変わります。
小さな成功体験が積み重なると、子どもの目の輝きも変わっていきます。
標準を固めてから、志望校レベルへ
この本で土台を作り、週末だけ応用演習を足す。
焦らず、でも止まらず進めば、中堅校合格へ現実的な距離感で近づけます。
家庭学習でも、やり方次第で図形は乗り越えられます。
次に読むなら、関連教材のレビューもチェック
図形と相性の良い計算力や文章題の強化も、得点の安定につながります。
わが家が使って良かった教材レビューも、よかったら続けて読んでみてください。
≪教材レビュー≫
お子さんに合う一冊が、きっと見つかります!
よくある質問と回答
Q1. この教材だけで図形問題は十分に対策できますか?
A1. 基礎から標準レベルまでの図形対策としては十分ですが、志望校が難関の場合は別途応用問題集や過去問を組み合わせると効果的です。特に受験直前期は本書で土台を固めつつ、志望校の出題傾向に合わせた練習を追加することで、より安定した得点が期待できます。Q2. 子どもが図形を苦手としている場合、どのタイミングから始めればよいですか?
A2. 苦手意識が強い場合は、学年に関係なく早めに取り組み始めることをおすすめします。特に高学年になると図形の出題範囲が広がるため、低学年や中学年から少しずつ視点の持ち方を練習しておくと、後の学習がスムーズに進みます。Q3. 親が図形に自信がない場合でもサポートできますか?
A3. 本書は解説が丁寧で、補助線や考え方がステップごとに示されているため、保護者が事前に読めば短時間でも要点を理解できます。子どもに丸投げするのではなく、一緒に「なぜそうなるのか」を確認する時間を作ることで、親子双方の理解が深まります。Q4. 1日の学習時間はどれくらいが理想ですか?
A4. 無理なく続けるためには、1日15〜20分程度で見開き1単元を目安に進めるのがおすすめです。短時間でも集中して取り組めば十分な効果が得られ、生活リズムを崩すことなく毎日継続する習慣が身につきます。Q5. 他の算数教材と併用する場合、どのように組み合わせればよいですか?
A5. 図形以外の計算力や文章題の強化も必要なため、曜日ごとに分野を分けて学習すると効率的です。本書で図形を扱う日は、他の分野は短時間で復習する程度にとどめると負担が軽くなり、全体の学力バランスを崩さずに進められます。