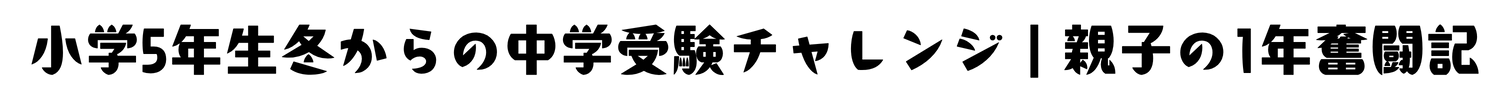【中学受験】理科の基礎を固めて得点力UP!親子で続けたおすすめ理科教材7選
はじめに|理科の「わからない」を「楽しい」に変える第一歩
我が家の中学受験でも、理科だけは後回しになりがちで、「何をどう勉強すればいいの?」と悩みました。特に理科の基礎知識や仕組みの理解が弱いと感じたとき、まず土台をしっかり固めることから始めました。
この記事では、親子で無理なく続けられ、実際に効果が感じられた理科教材を7冊厳選し、家庭学習での活用方法や教材のメリットも交えてご紹介します。
📚 実際に使って良かった理科教材7選|体験レビュー付き
① 中学受験 すらすら解ける魔法ワザ 理科・基本から始める超入門
理科嫌いの我が子でも手に取りやすく、基礎知識の定着と仕組み理解に効果がありました。図解と簡潔な解説が親子で理解を共有しやすく、家庭で安心して取り組める1冊でした。塾なしでも理科の土台作りに最適でした。
- 基礎知識を体系的に学べる
- 図やイラスト中心で理解しやすい
- 親が教える手引としても使える
② 基礎からしっかりわかる カンペキ!小学理科(技術評論社)
難関中学受験でも対応できる知識が網羅されており、図解中心で深く理解できる構成。我が家では苦手単元の理解をガイドするために活用し、学び直しにも最適でした。
- 難関校対応の理科知識が整理されている
- 図と色使いで直感的に学べる
- 独学でも理解可能な構成
③ 塾技100 理科(文英堂)
現役塾講師がまとめた「塾技100」は、重要ポイントがコンパクトにまとまっていて、効率的に身につくのが魅力。毎日の復習や短時間学習にもぴったりです。
- 塾のノウハウを家庭で活用できる
- 頻出事項が100の技に整理されている
- 短くても学習質を維持できる
④ 受験理科の裏ワザテクニック(文英堂)
理科の解法や計算問題をテクニック中心に学べる1冊。計算が苦手な子でも、考え方や解き方が見えるようになりました。我が家は苦手単元を克服するサブ教材として使いました。
- 計算問題の解法が体系化されている
- 親子で取り組みやすい手順形式
- 苦手分野の克服に直結
⑤ 中学入試基礎ドリ 理科[植物・動物・人体]
項目ごとに同じ知識を角度を変えて反復できる構成で、基礎知識が確実に定着する仕組み。間違えても何度も癒着して確認できる宿題形式が我が家でも好評でした。
- 基礎知識を繰り返し学習できる
- 復習用にコピーして繰り返し使える
- 5・6年後半でも無理なく始められる
⑥ 自由自在 理科(受験研究社)
図や写真が豊富で、小学生でも視覚的に理解しやすい内容。初めて理科を学ぶ子にも適しており、受験前の確認教材にも便利でした。家庭で読み物として楽しめる構成です。
- カラー図鑑のように興味を引き出す
- 重要ポイントが見開きで整理されている
- 勉強嫌いな子にも入りやすい
⑦ 中学入試 でる順過去問 理科(旺文社)
頻出パターンを厳選して収録しており、入試直前の演習に最適。実戦力をつけたい時期に集中して取り組めました。子どもも「見たことある」安心感で進められました。
- 実戦演習の感覚を養える
- パターン認識力を鍛える
- 演習量の調整がしやすい
家庭学習で気をつけたこと|親目線の勉強法ポイント
・毎日の少しずつで継続習慣を作る
我が家では、朝や夜の10分を理科の読み物や問題演習に使いました。毎日少しずつでも続けることで学びの質が上がり、苦手単元の克服につながりました。
・「なぜ?どうして?」を問いかける習慣
答えを丸暗記するのではなく、「どうしてそうなるの?」と考えることを習慣化。教材によっては補助線やイラストを使って説明することで、仕組み理解が深まりました。
・親子で一緒に取り組んで対話を重ねる
理科の問題を声に出して読んだり、図やイラストを見ながら親子で状況を確認することで、理科が「共有の時間」になりました。
教材選びの5つのポイント|理科を得意科目にするために
- 基礎知識がしっかり整理されている教材を選ぶ
- 図解やイラストで視覚的理解を助ける構成
- 反復学習ができる量と構成が備わっている
- 計算・暗記・思考のバランスが良い教材
- 親も一緒に使いやすく、声かけしながら取り組めるもの
まとめ|理科は土台と対話がすべてを変える科目
理科はセンスよりも、正しい教材と習慣、そして「考えて学ぶ姿勢」が伸びる力を決める科目です。今回ご紹介した7冊は、どれも基礎から応用まで無理なく続けられ、親目線で「この教材なら子どもが変われる」と感じられたもの。
家庭で取り組むときは、「今日はこれだけ」「なぜ?どうして?」を問いかける習慣を大切に。一緒に学ぶことで、理科が苦手だった子でも楽しめる科目になります。ぜひじっくり取り組んで、得点力アップを目指してください。