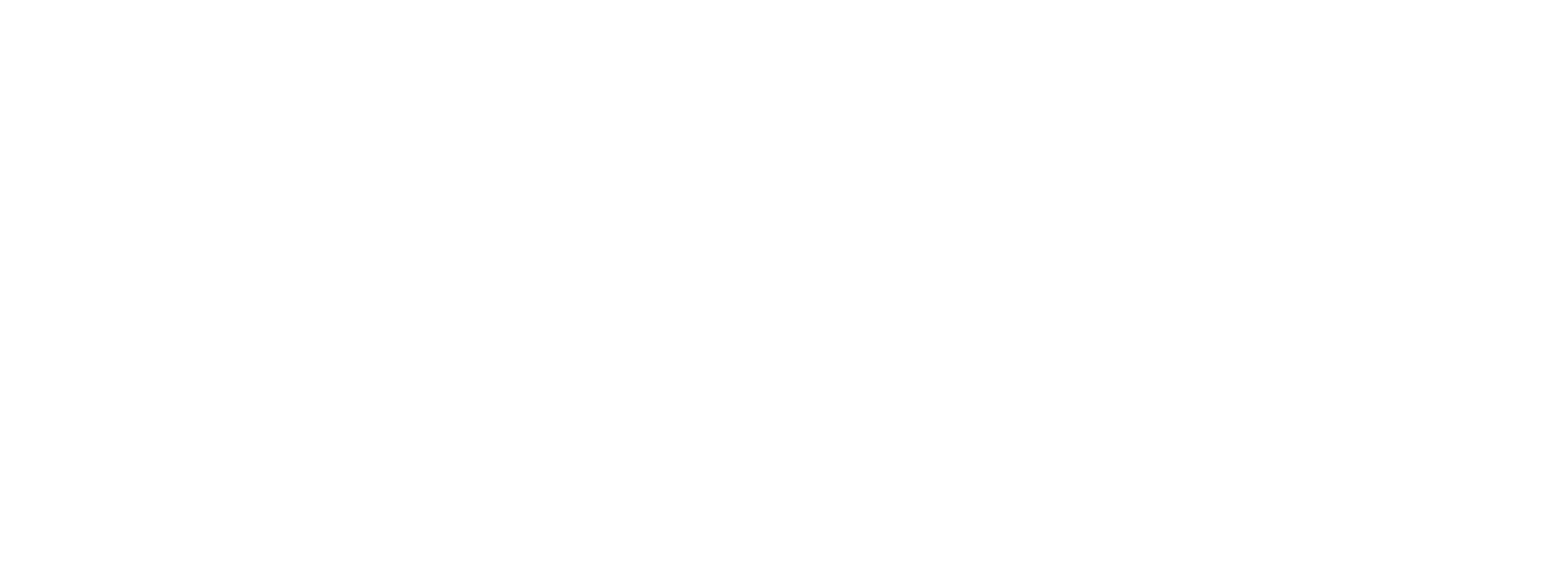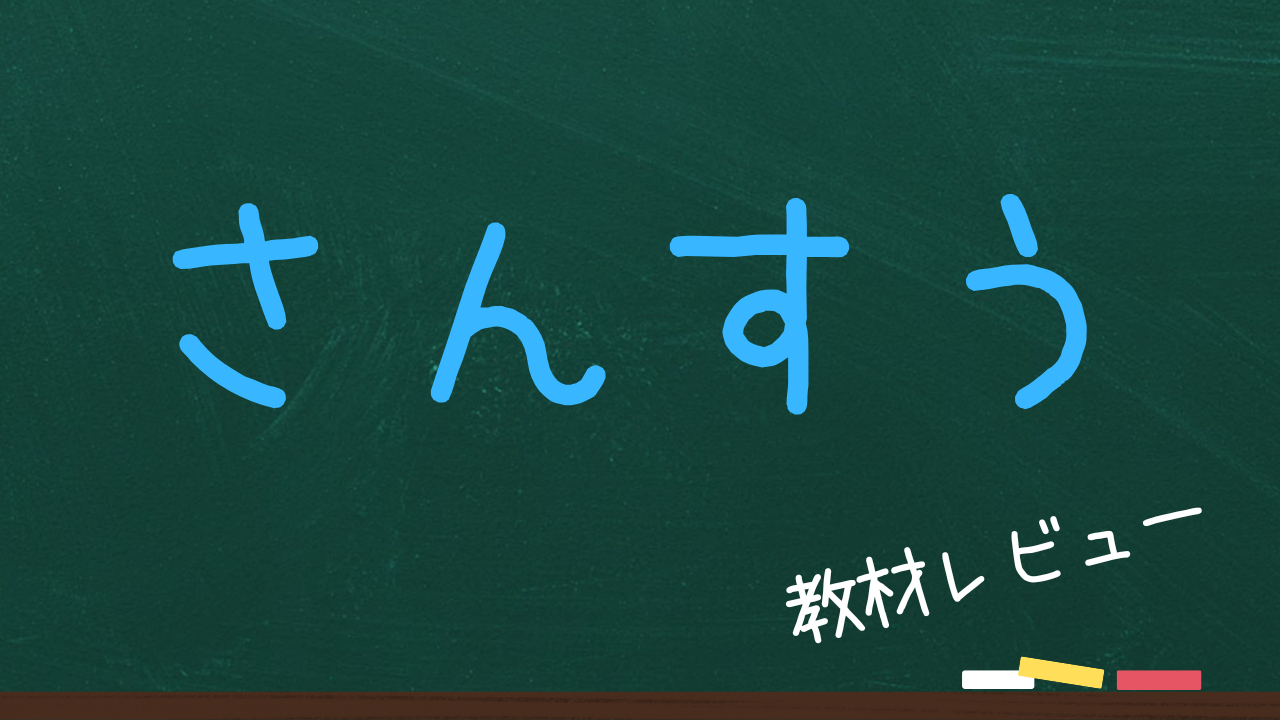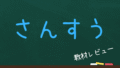『中学入試 算数 塾技100』はどんな本?
「分かっているのに本番で手が止まる」「同じミスを繰り返す」——そんな悩みが続いた時、息子と出会ったのが『塾技100』でした。
入試でよく出る“解き方の型”を短い解説と例題で身につけ、すぐに練習で定着させる流れは、忙しい家庭にもやさしい設計。
母の私が隣で見ていても、解く順番がはっきりと言葉で説明できるようになる変化を感じました。
ねらいとコンセプト
入試頻出の考え方を100個の「技」として体系化し、問題を見た瞬間に取るべき作戦を選べるようにすることを狙っています。
思考の道筋を言語化し、再現性を高める設計です。
対応分野とレベル感
割合・比・速さ・数の性質・平面図形・立体・場合の数まで幅広くカバー。
標準〜やや応用レベルを中心に、入試本番で得点に直結しやすい内容です。
学びやすい紙面構成
「技の要点」→「例題」→「練習」で最短距離の流れを作り、各技が独立しているため、弱点だけをつまみ食いで学び直すこともできます。
使って感じたメリットと気をつけたい点
実際に親子で取り組み、良かったところと注意したいところが見えてきました。
正直な母目線の感想です。
メリット:初見での“立ち上がり”が速くなる
出題の見かけが変わっても、同じ技で攻められる安心感が生まれます。
最初の数分で手が動き、ミスも減りました。
メリット:短時間でも手応えが積み上がる
1技ごとの分量が適切で、平日も無理なく進みます。「今日も一つ覚えた」が翌日の自信につながりました。
注意点:計算土台と読解は別で補強を
技が分かっても計算が乱れると点になりません。
計算ドリルや語句の確認を並走させると効果が安定します。
口コミ・レビューから見える評価
「手が止まらなくなった」「解法の引き出しが増えた」という声が多く、直前期の総仕上げや弱点単元の底上げに使われています。
一方で、基礎が揺らいでいる段階だと難しく感じるという意見もあり、土台作りと併用すると満足度が高い印象です。
高評価のポイント
技の整理が明確で、入試本番の得点行動に直結しやすい点が支持されています。
短い解説で視点がつかめるのも好評です。
購入前に知っておきたい点
一部の技は抽象度が高く、図や言葉の補足が必要な子もいます。
親の一言「なぜこの式を選ぶの?」が理解を深めます。
総合印象
「標準問題で確実に取る」を徹底できる良書。
模試の安定感が増し、合否ラインの押し上げに効きます。
効果的な使い方|今日から実践できる進め方
同じ教材でも、使い方で伸び方は変わります。
我が家のやり方を、そのまま真似しやすい形でまとめました。
1日の分量とサイクル
平日は「技→例題→練習」を1〜2本、休日は復習を中心に。
同じ技で2〜3問だけ類題を追加すると自走力が安定します。
間違い直しのコツ
その場で直さず翌日再挑戦。忘れかけた頃にもう一度解くと、技の理解が本物になります。
できたらチェックを外す仕組みに。
過去問への橋渡し
習得した技を使う大問を1題だけ過去問から選び、「同じ視点で攻められるか」を確認。
成功体験が本番の安心感に直結します。
この本が合うタイプと、別の選択肢
お子さんの性格や現在地に合っているかは大切なポイント。
最初に見極めると遠回りを減らせます。
相性が良いタイプ
基礎は触れてきたのに得点が安定しない、解き始めの一歩が遅い、同型問題でミスを繰り返す——そんな子にぴったりです。
もう一歩の工夫
技カード化や要点メモを作ると想起が速くなります。
音読で「技の言葉」を口に出すと、試験中の再現率が上がります。
別教材を先にすべき場合
四則計算や分数・小数が不安定な段階、文章の読み落としが多い段階は、基礎計算や読解の補強を先に。
土台が整うと本書の伸びが一気に加速します。
他教材との役割分担と併用のコツ
一冊で完結させるより、役割分担で回す方が効率的です。
基礎の反復はドリル、考え方の整理は本書、実戦慣れは過去問という流れが王道です。
計算・図形の土台づくり
毎日10分の計算練習と、図形は作図や補助線の練習をセットに。技の再現率が大きく変わります。
直前期の使い所
頻出技だけをリスト化して総点検。
時間を計って「技の選択→手を動かす」までを一気通貫で練習します。
学習管理の見える化
習得した技にチェック、未定着は★マーク。★が2つ以上の技だけ週末に再挑戦し、復習迷子を防ぎます。
まとめ|“型”が身につくと、点は安定する
合否を分けるのは才能ではなく、正しい“型”を落ち着いて再現できるかどうか。
『塾技100』はその型を身につける近道でした。今日の一技が、明日の一点につながります。
親子で無理なく、でも確実に積み上げていきましょう。
-
『算数 塾技100』は入試頻出の解法を100個の「技」として整理し、初見問題でも迷わず手を動かせる思考の型を身につけられる教材です。
-
各技は要点解説・例題・練習の流れで短時間でも効率よく学べ、平日1〜2本のペースでも着実に定着が可能です。
-
実践では過去問と結びつけて復習し、同型問題への対応力や試験中の初動スピードを大幅に向上させます。
-
基礎計算や読解が不安定な場合は別教材で土台を固めてから本書に取り組むことで、効果を最大限引き出せます。
-
他教材と役割分担し、学習管理の見える化や直前期の総点検を組み合わせることで合否ラインの押し上げが期待できます。
よくある質問とその回答
Q1. 『算数 塾技100』はいつから使い始めるのが効果的ですか?
入試まで半年〜1年程度の時期が最も効果的です。基礎計算や図形の読み取り力がある程度ついた段階で取り組むことで、技の理解と定着がスムーズになります。早すぎると難易度が高く感じて挫折する可能性があるため、時期選びは慎重にしましょう。
Q2. 毎日どれくらいの量を進めればいいですか?
1日1〜2技を目安に進めると、復習を含めても無理なく継続できます。急いで全てを終わらせるよりも、学んだ技を何度も繰り返し使えるようになることが重要です。特に苦手分野は意識的に間隔をあけて復習すると定着率が高まります。
Q3. 他の算数教材と併用しても問題ありませんか?
もちろん可能です。むしろ、塾技100は「解法の型」を身につける教材なので、基礎計算や文章題の読解力を鍛える教材と組み合わせることで総合力が伸びます。役割分担を意識することで学習効率が上がります。
Q4. 親はどのようにサポートすればいいですか?
まずはお子さんが習得した技を自分の言葉で説明できるか確認してあげてください。解法プロセスを言語化することで理解が深まり、試験本番でも迷わず使えるようになります。日々の声かけや進捗管理も大切です。
Q5. 難しい技に出会ったときはどうすればいいですか?
理解が追いつかない場合は、いったん後回しにして似たタイプの易しい問題で感覚を養うと効果的です。再挑戦の際には、例題を自分で解き直しながら「なぜこの技を使うのか」を意識すると、納得感を持って定着できます。