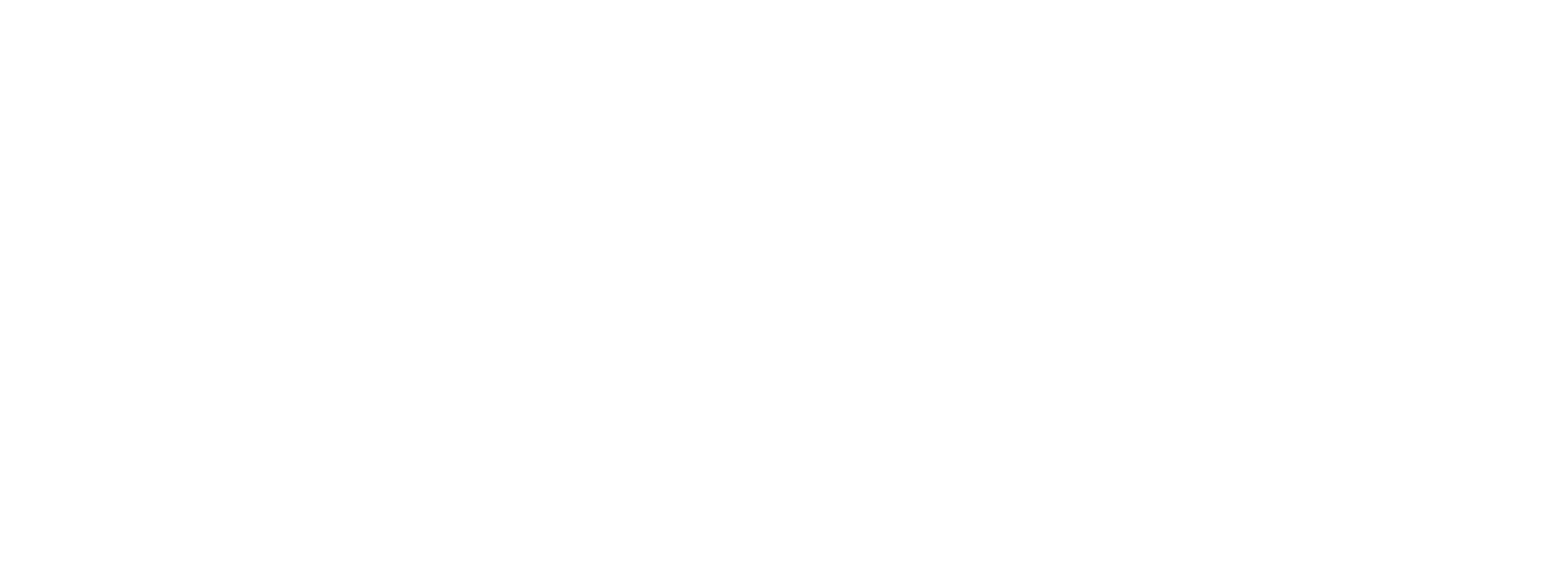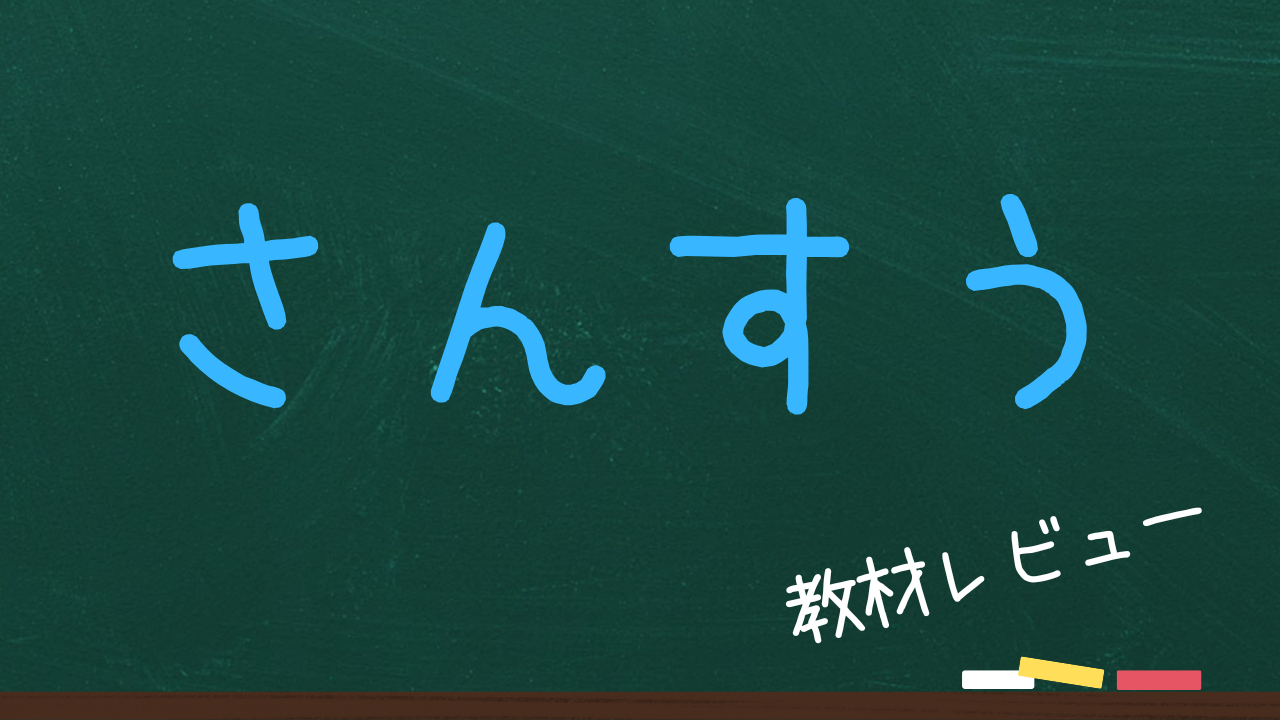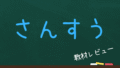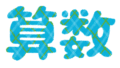中学受験の算数、特に基礎力を固めたいとき「どんな教材が一番効果的なのか?」と悩むご家庭は多いと思います。
今回は、私が実際に家庭学習で活用し、口コミでも評判の『基礎ドリ 算数[頻出小問]』を徹底紹介します。
特徴や口コミはもちろん、我が家での使い方のコツもお伝えしますので、最後まで読めば「今すぐ使ってみたい!」と思えるはずです。
この教材はどんな本?
出版社と基本情報
『基礎ドリ 算数[頻出小問]』は文英堂が出版している中学入試向け算数ドリルです。
価格は990円(税込)※2025年8月時点、B5サイズで持ち運びしやすく、64ページ前後の構成になっています。
対象学年とレベル感
対象は主に小学校高学年、中学受験を意識し始めたお子さん。
最難関ではなく、中堅〜やや上位校を目指す基礎固めにぴったりです。
教材の目的
基礎力をしっかり固めつつ、時間内に正確に解く力を身につけることが狙いです。
受験勉強の土台作りに向いています。
口コミ・評判まとめ
保護者からの高評価
「繰り返し解ける仕組みが便利」「段階的に難易度を上げられるので達成感がある」といった声が多く見られます。
子どもが自発的に取り組むケースも
問題量がちょうどよく、1回分が短めなので、子どもが自分から「もう1回やる」と言うこともありました。
デメリットの声
一部の保護者からは「応用問題が少ない」という意見もあります。
応用力を鍛えたい場合は、別の教材と併用がおすすめです。
教材の特徴とメリット
4回くり返しで定着率アップ
同じテーマを4回繰り返し解く方式で、自然と解法が身につきます。
1回目で間違えた問題も、4回目にはスムーズに解けるようになります。
スピードと正確さを同時に鍛える
制限時間を意識する構成なので、試験本番に必要な時間感覚を磨くことができます。
実際の入試問題も収録
最後のステップには過去の入試問題を掲載。基礎の確認だけでなく、実戦力も養えます。
効果的な活用法
毎日の短時間ルーティンに
1回分が短いので、朝学習や帰宅後の10〜15分で取り組むのがおすすめです。
間違えノートの活用
間違えた問題だけをピックアップし、別ノートで再度解くことで弱点克服につながります。
他教材との組み合わせ
応用問題集や過去問演習と組み合わせると、基礎+応用のバランスが取れます。
どんな家庭におすすめ?
塾は最小限で済ませたい家庭
塾の授業を受けられる時間が限られているご家庭でも、自宅で効率的に学習できます。
基礎固めを優先したいお子さん
応用に進む前に基礎を確実に固めたい段階にある場合、この教材が強い味方になります。
繰り返し学習が合う子
同じ問題を何度も解くことで安心感を得るタイプのお子さんに特におすすめです。
まとめ
『基礎ドリ 算数[頻出小問]』は、限られた時間でも基礎を固められる優秀なドリルです。
4回くり返し方式と実戦問題で、スピードと正確さの両方を鍛えられます。
中学受験の土台作りをしたいご家庭は、ぜひ一度手に取ってみてください。
-
『基礎ドリ 算数[頻出小問]』は文英堂発行で、中学受験向けに基礎力を定着させるための4回くり返し学習方式を採用した教材です。
-
1回分が短く取り組みやすいため、朝学習や帰宅後など限られた時間で継続でき、日常学習に無理なく組み込めます。
-
最終段階で実際の入試問題に挑戦できる構成により、基礎固めと同時に実戦感覚や時間配分の力も養えます。
-
保護者や利用者からは「繰り返しやすい」「段階的に学べる」と高評価が多く、子どもが自発的に学習する事例もあります。
-
中堅校を目指す家庭や塾時間が限られる家庭、基礎をしっかり固めたいお子さんに特におすすめできる一冊です。
よくある質問と回答
Q1. この教材は算数が苦手な子でも使えますか?
A. 苦手意識があるお子さんでも取り組みやすい構成です。問題は基礎から始まり、徐々にレベルアップするので「わかる」経験を積みやすく、自信につながります。難問中心ではないため、算数の土台を作るのに適しています。
Q2. 1日どのくらいの時間をかけるのが理想ですか?
A. 1回分が短めに作られているため、1日10〜15分程度で十分です。時間をかけすぎず、毎日続けることで効果が高まります。週末に少し多めに取り組むなど家庭のペースに合わせても問題ありません。
Q3. 学校の授業と並行して使えますか?
A. 学校の算数カリキュラムと大きく乖離していないため、並行しての使用は可能です。授業で習った単元の復習として使うと、理解が深まり、定着度が高まります。家庭学習の補強教材としても活躍します。
Q4. 他の教科の基礎ドリもありますか?
A. はい、同シリーズには国語や理科などの教科も用意されています。教科ごとに同じ「くり返し学習」形式を採用しているため、複数教科で活用すれば学習習慣を統一しやすくなります。
Q5. 途中でやめてしまった場合のリカバリー方法は?
A. 中断後は一度最初のステップに戻り、短い範囲を集中してやり直すのがおすすめです。学習記録をつけて進み具合を可視化すると、再開のモチベーションが上がり、継続しやすくなります。