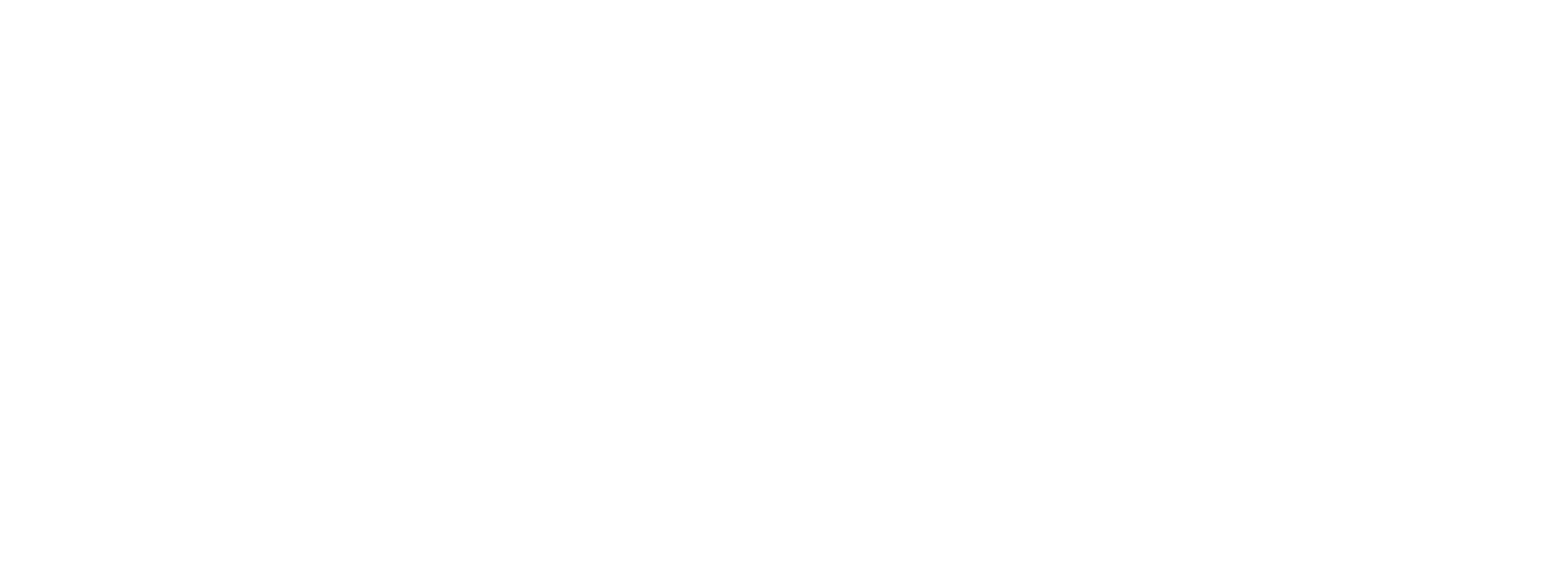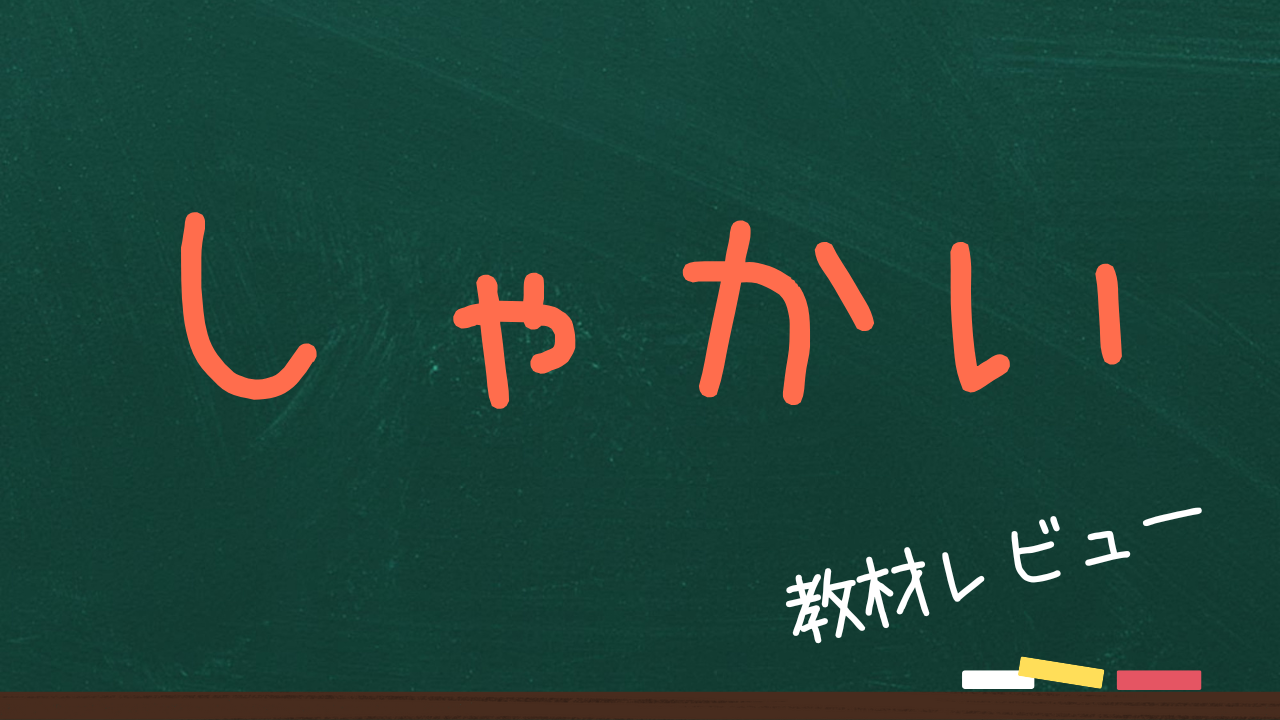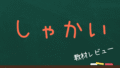『基礎ドリ 社会[歴史]』の特徴と基本情報
4回反復で「速さ×正確さ」を鍛える
最重要事項を角度を変えて4回くり返し練習し、短期間で基礎を固める構成。
時間を意識したトレーニング設計で、入試に必要な“即答力”の養成を狙います。
4回目は入試問題で実戦チェック
最後の回は実際の中学入試問題から重要問題を厳選。
知識の活用可否を実戦形式で確認でき、模試・過去問への橋渡しに使えます。
縮刷ページでコピー周回しやすい
解答冊子の後ろに本冊の縮刷が付属。
必要箇所だけコピーして何度でも反復でき、苦手単元の集中特訓がしやすいのが強みです。
口コミ・評判の傾向(要約)
良い声:基礎固め・継続のしやすさ
「基礎固めに最適」「同じ内容を形を変えて聞かれるので頭に入りやすい」「巻末のコピー用ページが便利」といった声が複数。
短時間で抜け漏れチェックができたという評価が目立ちます。
使って分かったコツ
反復を前提に“白紙を残す”運用(コピーやノート利用)と相性が良いという体験談が多く、1回で終わらせず周回するほど効果を実感しやすいという傾向があります。
注意点:思考・資料読み取りは別対策
本書は知識の即答化に主眼があるため、資料読み取りや記述重視の学校を受ける場合は、別教材や過去問演習で補うと安心です。
難易度・レベル感と到達イメージ
対象レベルは「基礎〜標準」
基礎〜標準の重要事項を取りこぼしなく固める狙い。
中堅校の合格点づくりに直結する“落とせない問題”の即答化に向いています。
どこまで伸ばせる?
4回反復で語句・用語の正確性とスピードが向上し、小テストや模試の得点安定化に寄与。
思考・記述系の伸長は別演習と組み合わせる前提が現実的です。
志望校別の使い分け
知識系比重が高い学校=本書中心で回転、
資料・記述比重が高い学校=本書で即答の土台→資料問題集や記述ドリルで補強、
という二段構えが王道です。
効果が出る使い方テンプレ(1日15〜30分)
1周目:音読+書き込みで輪郭づくり
用語を音読→すぐに書く。
はじめは満点にこだわらず、用語の形と意味のセット化を優先。
間違え箇所は付箋でマーキングします。
2〜3周目:弱点集中の「面回し」
単元を広く回しつつ、間違えた問題だけコピー再演習。
2〜3日あけて解き直すと忘却対策になり、効率よく定着します。
4回目:入試問題で“即答”を確認
制限時間を設定して解く→正誤だけでなく根拠を口頭で1フレーズ説明。
迷った選択肢の理由付けまで行うと本番の再現性が上がります。
学年・時期別ロードマップ
小4〜小5:歴史の流れ+頻出語の土台づくり
1日1単元×平日でOK。
年表・地図・人物をつなげ、出来事を「政治・文化・対外関係」で整理する癖をつけます。
小6 春〜夏:周回と確認テストで穴埋め
週2〜3単元を目安に一気に回し、週末は口頭チェック。
苦手単元は縮刷コピーでピンポイント反復します。
直前期:年代・文化史・近現代の詰め
頻出年号・文化史はカード化し、近現代は「出来事→理由→結果」の1行メモで因果を固定。
仕上げに過去問の類題で確認します。
併用設計:弱点を補うおすすめの組み合わせ
一問一答系で高速チェック
日々の隙間時間は一問一答系(赤シート対応など)を併用し、基礎ドリで書いて覚えた内容を素早く確認します。
資料集・地図・年表で「つながり」を強化
図版・写真・年表を使って出来事の位置関係や前後関係を可視化。
用語暗記が“地図上の出来事”として定着します。
模試・過去問との橋渡し
基礎ドリ4回目で実戦感覚を掴んだら、模試の見直し→過去問の基礎設問を先行攻略。
記述は別ドリルで段階的に慣らします。
つまずき対策:ここで差がつく3ポイント
時代の流れが混線する
旧石器〜奈良/平安〜江戸/明治〜現代の3ブロックに大枠化し、出来事を「政治・文化・対外関係」でひも付けて覚えます。
文化史が覚えきれない
人物・作品・時代を三点セットでカード化し、毎日口頭テスト。
似た名称は「区別メモ」を作って見比べます。
近現代の因果が弱い
「出来事→理由→結果」を1行で書き出す練習を継続。
条約名・戦争名・国内の変化を矢印で結ぶと記憶が安定します。
この教材が向く子・向かない子
向く子
短時間で反復したい/「書いて覚える」が合う/基礎〜標準の取りこぼしをゼロにしたい。
向かない子
資料読み取り・記述の比重が高い学校を第一志望にしており、思考演習を先行したい。
割り切りポイント
“まず即答の土台→次に資料・記述”と段階を分けると、本書の強みを最大限活かせます。